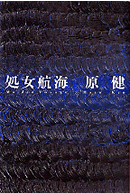
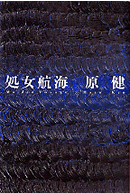 |
||||||
|
処女航海
|
||||||
|
著者
|
原健 | |||||
|
出版社
|
幻冬舎 | |||||
|
定価
|
本体価格 1500円+税 | |||||
|
第一刷発行
|
2001/10/30 | |||||
| ISBN4−344−00124−9 | ||||||
|
夢の中で電話が鳴っていた。 |
|||
|
|
|||
|
このページの画像、本文からの引用は出版社、または、著者のご了解を得ています。 Copyright (C) 2001 books ruhe. All rights reserved. 無断でコピー、転写、リンク等、一切をお断りします。 |