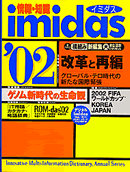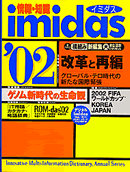|
【特別付録】
IT用語/カタカナ・略語辞典
世界を変える
lT(情報技術)を展望
一目でIT用語がわかるオール2色辞典
【特別付録】
ROM−das'02
[Webイミダス]アクセス権つき
[デジタルimidas]アクセス特典つき
世界史総合年表/20世紀&テーマ年表/国と地域のデータ/
20世紀を創った人びと/力タカナ語・欧文略語/英語雑学ほか
【折り込み4色地図】
アフガニスタンと周辺諸国/「同時多発テロ事件」から「アフガン空爆」まで
巻頭特集
ゲノム新時代の生命観
先端医療の現状
─―生命はどう扱われているのか─―
青野由利
毎日新聞科学環境部編集委員(医学…生命科学など担当)。1957年生まれ。フルブライト客員研究員(マサチューセッツエ科大学)を経て、東京大学大学院修士課程修了。著書に『遺伝子問題とはなにか』など。
現代の先端医療
最先端の科学知識を、治療や予防に応用する。医学がそのように進歩してきた以上、どの医療行為も初めは「先端医療」だったといってもいいだろう。
ジェンナーの種痘も抗生物質の投与も、最初は先端医療として始まったに違いない。
これらの医療はいずれも、これで治るかもしれないという「期待」と、患者が被るかもしれない「リスク」が隣あわせになっている。
いわば実験的医療である。
それは現在の先端医療でも変わらない。
では、最近の先端医療に何か特徴はあるのだろうか。
そう考えてみて思い当たることが二点ある。
一つは、「生命をどう扱っていくのか」という、人類全体に影響を与える問題を内包しているにもかかわらず、その土台となる考え方が定まっていない点。
そしてもう一つは、それぞれの先端医療が複雑にからみあっているという点ではないだろうか。
典型的な例として、「再生医療」「生殖補助医療」「遺伝子医療」の三つについて考えてみよう。
再生医療〜ES細胞の可能性
イモリやプラナリアは、しっぽがちぎれても自然に元に戻る。
病気やけがで細胞や臓器が壊れたときに、このような再生の原理を利用して治療しようとする試みが「再生医療」である。
この医療がクローズアップされる背景には、胚性幹細胞(ES細胞)と呼ばれる特別な細胞を作る技術と、クローン羊「ドリー」を作り出した体細胞核移植技術がある。
ES細胞は、受精卵が分裂を繰り返し、細胞の数が100個程度の胚になった時点で内部の細胞の塊を取り出し、特別な条件で培養して作り出す。
マウスでは以前から作られていたが、ヒトのES細胞は1998年にアメリカで初めて作り出された。
なぜ、一この細胞が注目を集めるかといえば、普通の細胞にはない「どのような細胞にも変化できる性質」を持っているからだ。
私たちの体を作っている普通の細胞は、皮膚なら皮膚、筋肉なら筋肉というように役割が固定されていて、皮膚の細胞はいくら分裂しても皮膚の細胞にしかならない。
ところが、ES細胞は条件次第で、皮膚の細胞にも筋肉の細胞にも、神経の細胞にも「変身」する潜在能力を持っている。
「万能細胞」と呼ばれるゆえんだ。
しかもES細胞は、この万能」性を保ったまま、シャーレの中でいくらでも増やすことができる。
パーキンソン病やアルツハイマー病の患者の脳で故障していたり、欠けていたりする細胞を、ES細胞から作り出して補うことができれば、治療に結びつく可能性がある。
脊髄を作り出すことができれば、脊髄損傷が治療できるかもしれない。
さらに技術が進めば、心臓や肝臓といった臓器をまるごと再生し、移植に使うことも不可能とはいえない。
ヒトES細胞・ヒトクローン胚の是非
ただし、細胞にせよ臓器にせよ、他人のES細胞から作り出したものは拒絶反応が問題になる場合がある。
これを解決する方法として考えられているのが、体細胞核移植技術で自分のクローン胚を作って、そこから自分自身のES細胞を作り出し、自分の細胞や臓器を「再生」する方法だ。
このように再生医療は、まさに最新の科学技術を応用した未来の先端医療だが、ヒトの胚を利用し、クローン胚作りまで検討する以上、「ヒトの生命をどのように扱うか」を改めて問わないわけにはいかない。
アメリカでは、「ヒトの胚は生命であり、それを壊すことは殺人にも匹敵する」と考えるグループと、「ヒトの初期の胚は細胞の塊に過ぎない」と考えるグループの間で激しい論争があり、国の方針はなかなか定まらなかった。
結果的にブッシュ大統領が採用した妥協案は、「すでに作り出されたヒトES細胞を使う研究は認めるが、新たにヒトES細胞を作ることや、その細胞を使うことは認めない」というものだった。
これは、再生医療をきっかけに、「ヒトの胚を壊すことの倫理性」と、「医学研究を妨げることの倫理性」がてんびんにかけられたことを示しているが、どこか一時凌ぎの解決策だという印象がぬぐえない。
一方、日本の政府はヒトES細胞の作製を認める指針を策定したが、指針作りの過程で、ヒトの胚に対する配慮の規定が「人の尊厳を冒すことのないよう」という表現と「礼意を失わないよう」という表現の間で、二転三転した。
これは、ヒトの胚の位置付けをあいまいにしたまま、再生医療を進めようとしていることの現れだと思える。
ヒトのクローン胚作りも大きな論争を呼び、イギリスは容認、アメリカは禁止の方向性を打ち出している。
日本は法律に基づく指針で禁止しようとしているが、その一方で、クローン胚の"親戚"であるヒトの胚細胞を核移植した胚や、動物の除核卵子にヒトの体細胞を核移植した胚の作製は認めるかどうか議論になった。
そして、これらの胚作製を許可するか、しないかを分ける主な基準は「新しい医療につながる有用性があるかどうか」であって、「生命をどのように扱うべきか」ではない。
|