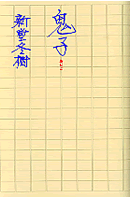
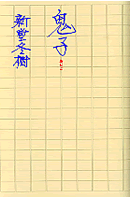 |
||||||
|
鬼子
|
||||||
|
著者
|
新堂冬樹 | |||||
|
出版社
|
幻冬舎 | |||||
|
定価
|
本体価格 1800円+税 | |||||
|
第一刷発行
|
2001/10/31 | |||||
| ISBN4−344−00125−7 | ||||||
|
1 大きな紙袋を片手に提げた二十代前半の若者が、こそこそと様子を窺いながらエントランスヘと踏み入った。 せっかく乗ってきたところなのに、執筆を中断しなければならない。 まだだ。 ひどい味に変わりはないが、缶のまま飲むのは袴田の美的センスが赦さない。 若者が、紙袋の中に突っ込んだ手を、メイルボックスに差し入れた。 「君、貼り紙が、眼に入らんのかね?」 「チラシの投函は厳禁、と、書いてあるだろう?」袴田は、六十世帯分のメイルボックスの上の壁に貼られた、黄色のマジックで縁取られた黄緑のマジックで書かれた貼り紙を指差し、低く威厳のある声で署めた。 注意書きは赤いマジックを使うのが一般的だが、袴田は、サラ金の取り立てを彷佛とさせる粗暴で品性に欠ける赤文字を嫌った。 「待ちなさい」脇を擦り抜けようとする若者の、半袖から伸びた生白い腕を掴んだ。 口うるさい居住者に文句を言われるのは、管理人である自分なのだ。 午前九時から午後五時までの勤務時間内は、部外者が自分の許可なしに勝手なまねをすることは赦されない。 若者が、紙袋から一枚のチラシを掴み、怖々と差し出した。 90分、15000円、チェンジOK、ノーサック応相談、ピチピチギャル多数在籍、などの低俗な活字が並ぶ淫らな内容とショーガールという店名から袴田は、若者の投函しているチラシはデートクラブのものだろうと見当をつけた。 なんという卑狼な写真、なんという低俗な言葉─―みるに堪えなかった。
|
|||
|
|
|||
|
このページの画像、本文からの引用は出版社、または、著者のご了解を得ています。 Copyright (C) 2001 books ruhe. All rights reserved. 無断でコピー、転写、リンク等、一切をお断りします。 |