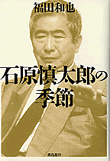 |
||||||
|
石原慎太郎の季節
|
||||||
|
著者
|
福田和也 | |||||
|
出版社
|
飛鳥新社 | |||||
|
定価
|
本体価格 1500円+税 | |||||
|
第一刷発行
|
2001/07/14 | |||||
| ISBN4−87031−472−X | ||||||
|
第一章 時代精神の体現者 戦後史の十字路に立ちつづける 【際立った存在感】 私はこれから石原慎太郎氏について一冊の本を書き出そうとしています。 石原氏への期待の現われといってよいでしょう。 おそらく戦争が終わってこの方、氏に対抗できるのは長嶋茂雄氏ぐらいではないでしょうか。 なぜ石原氏はかくも長い期間─むろんその間には多少の浮滋はあったのですが─にわたって人々の強い関心を集めつづけてきたのか。 けれどももっと重要なことは、石原氏が時代の節目節目に際立った存在感を示してきたということです。 【時代精神の「核」を体現】 かくも高名であり、多くの人が語っている石原氏について、なぜ今一冊の本を書かねばならないのか。 あるいは、政治指導者として首相として、石原氏の登場を待望する書物もたくさん出ています。 自分なりに氏の全体像を再構成してみたかったのです。 誰もがその時代の子であることを考えれば、石原氏のみならず、誰でもがある意味では時代精神の体現者ではあります。 だとするならば、やはり石原氏には、現在の日本がもっている時代精神の「核」のようなものが、いずれにしろ体現されているに違いない。 氏が集めている輿望は、現在の日本が乗り上げているデッドロックの本質ときわめて密接な関係をもつとともに、そこからいかに脱出するかという方向性とも関係があるのです。 |
|||