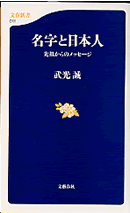
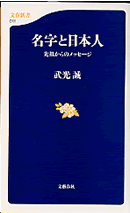 |
||||||
|
名字と日本人
|
||||||
|
著者
|
武光誠 | |||||
|
出版社
|
文春新書/文藝春秋 | |||||
|
定価
|
本体価格 660円+税 | |||||
|
第一刷発行
|
1999/11/20 | |||||
| ISBN4−16−660011−7 | ||||||
|
はじめに 日本には二九万通り余りの名字がある。 その中には、限られた家だけが用いる難読の名字も多い。 西ヨーロッ。パ、中国など他の民族にも、日本の名字に似た、家々を区別する符号はある。 しかし、それは一つの民族でせいぜい数百種類ていどの、日本のものにくらべてはるかに単純な形をとっている。 日本人が多様な名字を伝えてきたことは、私たちがそれを祖先からのメッセージとして重んじつづけたことを意味する。 しかし、現在の名字には、あいまいでわかりにくい部分が多い。 それが一つの家の由来をあらわすとも、あらわさないともいえるのだ。 これまで、太田亮氏や丹羽基二氏をはじめとするいく人もの名字研究家が出た。 その業績によって、私たちは日本人の名字の全体像を気軽に知ることができるようになった。 また、かれらによって多くの珍しい名字が紹介された。 ただ、そういった研究家たちの書いたものを見ても、これだけ多様な名字ができた過程や、その意味については、十分に説明づけられていない。 私は、名字は鎌倉幕府の武家支配によって作られたとする視点から、本書で今日までの名字の歴史を明確に説明したい。 古代の農民は大伴部、日下部などの「姓」をもっていたが、のちにそのような姓を失い、鈴木、佐藤といった武士が広めた「名字」を代々伝えるようになった。 これは、武家支配の成立によって日本が一つにまとまったことを意味するものである。 ゆえに、名字の発生は、武士の登場と鎌倉幕府の成立にかかわる日本史上の重要な出来事としてとらえるべきである。 本書を読んでもらえば、そのことをおわかりいただけると思われる。 名字がきわめてあいまいな性格をもつため、本書はつぎのような書きかたをとった。 まず、「名字の不思議」の章をおき、名字がどのような性格のものかを説明した。 名字自体に興味をもつ方ならば、ここを読むだけで知りたいと考えることの大半をつかめると思われる。 ついで、「第二章武士団と名字の形成」、「第三章名字の全国的普及」、「第四章江戸幕府の苗字・帯刀の制限」、「第五章世界の姓氏と明治の戸籍法」で、武家政権とのかかわりを中心に、名字の歴史を述べた。第五章では他の民族の「姓氏」とくらべつつ日本の名字の特徴も明らかにした。 そして最後に、「第六章先祖探しと名字」を記し、名字の由来を探る先祖探しの方法を紹介した。名字に関心をもったうえでこの部分を手がかりに先祖探しをしてみると、日本の歴史を深く理解できるようになる。 名字は、昔の人が現代の私たちに残してくれた貴重な遺産である。
|
|||