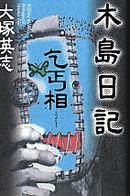
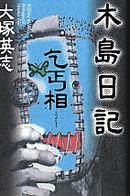 |
||||||
|
木島日記 乞丐相
|
||||||
|
著者
|
大塚英志 | |||||
|
出版社
|
角川書店 | |||||
|
定価
|
本体価格 1200円+税 | |||||
|
第一刷発行
|
2001/11/10 | |||||
| ISBN4−04−873327−3 | ||||||
|
近頃のミステリー小説では連続殺人とか大量殺人が約束事のようになっている。 けれども統計上のデータからいえば十代の少年たちは昔の方がずっと人を殺す連中が多かった。 だから例外として起きる十四歳や十七歳の殺人はその意味では珍しく、大きく報道される。 犠牲者の数が十人を越えるのは新左翼のセクトの集団リンチ事件や、カルト教団のテロといった組織による、どうにも個人の責任が曖昧な状況下で起きた事件のみで、連続殺人事件と名付けられた戦後史上の事件に於いてでもせいぜい被害者の数は四人とか最高で八人である。 サイコサスペンスでお馴染みとなったプロファイリングにしてもその中身は実のところ、過去の類似事件から導き出される統計上の偏差に基づいて行う類推作業を言うのだが「連続殺人者の八八%は男性で、ハ五%は殺人、最初の殺人を犯した年齢は二十八・五歳」などという分析が可能なのは逆に言えば統計を可能にするに充分な程度には過剰殺人者がいることを意味している。 だが戦後の日本に於いては連続殺人、大量殺人の名にかろうじて値する事件はどう見積もっても一桁台でしかない。 日本人はただフィクションの中でのみ人を殺し続けているのだ。 だからミステリー作家がもう少しこの国の現実を反映した小説を書こうとするのなら戦後の日本人は何故、人を殺さなくなってしまったのか、という謎こそ解明すべきなのだ。余計なお世話かもしれないが。 前ふりが長くなってしまったが、ぼくが今日の日本を支配するらしい奇妙なサイコサスペンス史観に敢えて疑念を呈したのはそうでもしておかないと今回紹介する挿話がただのありふれた荒唐無稽な物語としてしか受けとめられないに違いないと危惧したからだ。 折口信夫博士のものとぼくが勝手に決め込んで、小説の素材に流用している例の「日記」に書かれたその挿話はただ「根津の話」とのみ題され、それから資料か何かのつもりなのか三葉ほどの変色した新聞記事の切り抜きが同じ頁に挟み込まれている。 新聞の日付は全て昭和十三年五月二十二日であり、その内の一つ「讀賣新聞」と青インクで記された切り抜きには「廿八人を猟銃で射殺岡山に殺人の大レコード」という見出しが認められる。 〈【岡山電話】廿一日午前二時四十分ごろ岡山縣苫田郡西加茂村字行重都井睦雄(二二)が突如起き上がり床の間にあつた獵銃と日本刀をもつて傍に就寝中の養母いそ(七五)をはじめ一家を惨殺したうへ近隣のもの合計廿ハ名を片っ端から射殺又は惨殺し、三名に重輕傷を負はせたうへ悪鬼の如き形相で獄銃と血刀を携へたまま山林中に逃げ込み平和に寝静まつてゐた山村は一瞬にして恐怖の巷と化した。 |
|||