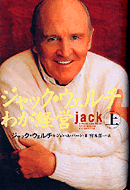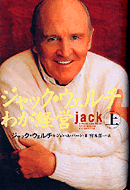|
著者注記
自伝の冒頭にこんなことを書くのはおかしいと思われるかもしれないが、正直なところ、私は一人称を使いたくない。
私がこれまでの人生でなし遂げてきたことのほとんどは、周りの人たちとの共同作業だからだ。
しかし、この種の本を書くためには、本当は「われわれ」のほうがふさわしくても、語り手として「私」という言葉を使わざるをえない。
私は苦楽をともにしてきた人すべての名前を出したいと思った。
少しでも名前を削ろうとする編集者は強く反対した。
さんざんやり合ったあげく妥協が成立した。
巻末の「謝辞」がずいぶん長くなったのはそのためだ。
本書を読みながら「私」という言葉に出くわすたびに、私が失念しているかもしれない同僚や友人やその他の人たちが「私」のなかにいるのだということを、どうか忘れないでいただきたい。
*日本語版では「謝辞」は下巻に収録。
プロローグ
二〇〇〇年の感謝祭が終わった土曜日の午前中、私はずっと「つぎの男」を待っていた。
それは、私の後継者、ゼネラル・エレクトリック(GE)の次期会長兼CEO(最高経営責任者)を意味する符牒だった。
前日の金曜日の夜、取締役会はジェフ・イメルトが私の後を継ぐことを全会一致で承認した。
私はすぐにイメルトに電話をかけた。
「いい知らせがある。明日、家族といっしょにフロリダに来て、週末をこっちで過ごさないか」何の話なのか、イメルトにはわかっているようだった。
おたがいにそれ以上のことには触れず、フロリダまでの足の手配を私自身がしたことを伝えた。
土曜日の朝、私は待ちきれない思いだった。
懸案の後継問題はようやく決着がついた。
イメルトの車がわが家の車寄せに入ってきたとき、私はすでに表に出ていた。
満面に笑みをたたえたイメルトが車から降りるのを待ちかねて、私は彼の肩に腕をまわし、二〇年前にレグ・ジョーンズ(私の前のGE会長)に言われたのと同じセリフを言った。
「おめでとう、ミスター・チェアマン!」抱き合いながら、かつて通った道に舞い戻ったような気がした。
コネティカット州フェアフィールド(本社)の私の部屋にジョーンズが入ってきて、私がいまイメルトを抱きしめているように私を抱きしめてくれた日のことが、まざまざと甦ってきたのだ。
ジョーンズはふだん、人を強くどころかちょっとでも抱きしめるようなことはなかった。
それがその日は、笑顔で私をしっかと抱きしめた。
一九八○年の十二月のその日、私はアメリカでいちばん幸せな男、間違いなくいちばん運のいい男だった。
何でもやりたい仕事をひとつ選んでいいと言われても、やはりこれ以外にはないだろう。
それは、航空機エンジンや発電機から、プラスチックス、医療機器、金融サーピスにいたるまで、信じられないほど多岐にわたる事業を統括する仕事だった。
GEがつくるもの、GEがすることは、ほとんどすべての人にかかわっている。
CEOという仕事で何よりも重要なのは、七五パーセント近くが人にかかわることで、その他のことはこ五パーセントにすぎないということだ。
私は、世界でも有数の頭脳や創造力そして競争力を持つ人たちと働いてきた。
GEには、私よりもはるかに頭のいい人たちがたくさんいた。
GEに入社した二九六〇年、大それたことは考えていなかった。私はそのとき二十四歳。
博士課程を終えたばかりの駆け出しのエンジニアだった。
当初の年俸は二万と五〇〇ドル。
三十歳になるころには、三万ドルはもらえるようになりたい。
私に目標といえるものがあったとすれば、その程度のことだった。自分の仕事にすべてを注ぎ込み、仕事をこなすのは楽しかった。
そのうちだんだんと昇進していくにつれて、目標も高くなり、一九七〇年代半ばになると、いつの日かGEの項点に立つ日が来るかもしれないと思うようになった。
風は逆風だった。私はGEになじまない、異端児にすぎると、同僚の多くは思っていた。
私は歯に衣を着せず、思ったことをずばずば言う人間だった。
気が短く、多くの人の神経を逆なでした。私の言動は常軌を逸していた。
成功の大小を問わず、事業の成功を祝うパーティーが会社の近くのバーでよく開かれたが、とくにそうした場で、私の振る舞いは異色だった。
ただ幸いなことに、GEには、そんな私に目をかけてやろうという度量のある人間がたくさんいた。レグ・ジョーンズもその一人だった。
表面上、私とジョーンズほど違って見える人間はいないだろう。
イギリス生まれのジョーンズは品位も威厳もあり、その物腰は政治家然としていた。
|