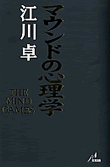 |
||||||
|
マウンドの心理学
|
||||||
|
著者
|
江川卓 | |||||
|
出版社
|
THE MASSADA | |||||
|
定価
|
本体価格 1400円+税 | |||||
|
第一刷発行
|
2001/8/7 | |||||
| ISBN4−88397−070−1 | ||||||
|
ストレートはどのくらい「真っすぐ」なのか? 通常の真っすぐの握り(フォーシーム)でボールを持ち、オーバーバンドで手首のスナップをきかせて投げた速球はバッターの手もとでホップしながらキャツチャーのミットに吸い込まれていきます。 答えは「ノー」です。 アメリカ大リーグのジアマッティ・前コミッショナーの依頼でイェール大学の物理学者ポール・アデア博士が著した『べ-スボールの物理学』(中村和幸訳、紀伊国屋書店刊)によれば、時速一四五キロでプルートに向かうバックスピンのかかっていないボールは、十八・四四メートル進む間に引力の関係で実際には九十一センチ沈んでいろのだそうです。 それを真っすぐな軌道であるかのように思い込んでいるのは、引力によって生じるゆるい落下曲線を真っすぐなものと見てしまう習性が私たちの知覚に組み込まれているからです。 さて、時速一四五キロのバックスピンのかかっていないボールは一八・四四メートル進む間に九十一センチ沈みます。 しかも、その揚力は残り四・五メートルのところにきて急速に生じるので、バッターの手元に来てホップしているように見えるのです。 これを直径七センチほどのバットで打ち返すことは至難のワザです。 しかし、スピンがうまくかかっていない場合(つまりボールのキレがイマイチなとき)は、十分ホップしないので、通常十三センチホップするのが十センチぐらいになってしまいます。 速球派といわれるピッチャーがタマの回転を気にするのは、いいときは空振りとポップフライの山を築くのに、キレが悪いときは一転してポップフライがホームランになる危険性があるからです。 前述の『べ-スボールの物理学』によれば、バットがボールの中心線より五センチ下のところを把えれば、打球はバックネット後方の二階スタンドに飛び込むファールになりますが、ボールの中心線よりニセンチ下のところをバットが把えれば、打球は四十五度くらいの角度で外野に飛ぶ耐空時間の長いホームラン性の大飛球になります。 もし、これがボールの中心線より二・五センチ下のところに当たれば、五十度くらいの角度で打ち上げられた大きな外野フライになり、ボールの中心線より一・五センチ下のところをバットが把えれば、三十五度くらいの角度で弾丸ライナーとなって外野手の頭の上を越えていきます。 では、フォーシームではなくツーシームで握って投げた場合は、ボールにどのような回転が生じ、どのような軌道を描いてキャッチャーのミットに吸い込まれるのでしょう。 これだと、もろに空気抵抗をうけることになるのでボールはバッターの手もとに来て沈みだし、ホップするボールより十センチから十五センチくらい低いところを通ってミットに収まります。 このバッターの手もとでおじぎする速球を打ちにいけば、当然ゴロが多くなります。
|
|||