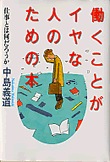|
はじめに
あとわずかの命
それは今夜かもしれず、明日かもしれず、明後日かもしれず、一週間後かもしれず、一年後かもしれず、一〇年後かもしれず、運のいい人は五〇年後かもしれない。
しかし、あなたは確実に死んでしまう。
あなたはこの地上ばかりか、この宇宙の果てまで探してもいなくなる。
そして「生」を受けたこのチャンスはたぶんただ一度かぎり。
もう二度とあなたが「生きる」ことはない。
こうした残酷な状況の中で、ではあなたは何をすべきなのだろうか?生きるかぎり、働かなければならないとすると、どのような仕事をすべきなのだろうか?というわけで、「仕事」についてこれから語ろうとする私がメッセージを送りたい相手は、失業中の身であって、どうしたら仕事にありつけるかという人ではない。
そういう人はコンナ本を読んでいる暇があったら、職業安定所にでも行って相談するほうがよろしい。易者にみてもらうほうが、まだマシかもしれない。
本書の読者として私が想定しているのは、次のような人々である。彼らとの(架空の)対話によって本書は成立している。
(A)
法学部の学生(男)だが、留年を繰り返しているうちに、二五歳を過ぎてしまった。格別勉強してこなかったし、法学に特別興味もないので大学院に進んでもしかたない。
司法試験や公務員試験は受かりそうもないので、はじめからあきらめている。といって、いわゆるサラリーマンにはなりたくない。あらゆる人間関係が煩わしく、会社という組織にガンジガラメになって生きるのが恐怖なのだ。
会社員の半奴隷のような薄汚い生態が厭でたまらない。
だから、なるべく就職を先送りにしたい。誰ともかかわらずひっそり暮らしたい。できれば一生寝て過ごしたい。
そういう自分の希望にふさわしい場がないかどうか、ときどき頭がヘンになりそうなほど、来る日も来る日も考えているが、答えは見つからない。
(B)ほかの女性のように、なんの疑問もなく結婚し子供をもつという道を歩むことができない。
だから、会社に入ってみたが仕事にどうしても興味を抱けず、鬱々とした毎日である。
という間に、いつしか三〇歳をこえてしまった。
自分は何をしたいのか?そうだ、自己表現をしたいのだ。同人雑誌の仲間を見つけ最近小説を書きはじめ、それなりに充実しているが、このままやっていけるのか、将来の展望はまったくない。
だが、ほかの道は考えられない。
どうしたらいいのだろう?
(C)いままで、金のため妻子のため、それに社会から落後することが恐ろしいために、気乗りのしない仕事を続けていた。
それになんの生きがいも喜びも感じないままに、ずるずる続けてきた。
すでに人生半ばを過ぎ(四〇歳をこえ)、これからもこの仕事をだらだら続けていっていいものだろうか?
あと二〇年このつまらない仕事にしがみついて、さらに精気のない老後を迎えるのだろうか?
考えれば考えるほど、イライラはつのり「どうにかしなければならない」と思うのだが、何をどうしていいのかわからない。
いままで真の意味でみずから決断したことがないので(ただみんなのする通りにしてきただけなので)、ことここに至ってさえ、自分のほんとうの望みがわからないのだ。
そういう自分の情けなさに泣きたくなるほどだ。
(D)少し前まで、自分の人生はまちがっていないと確信していた。まじめ一本で働きつづけ、親から受け継いだ小さな会社を守り通した。
黙って私についてきてくれた妻には感謝以外の何ものもないし、二人の子供も結婚し、孫も授かり、はじめその気のなかった長男も私の後を継いでくれるという。
もう自分ほどの幸福者はいないと思っていた。
だが、先日久しぶりに人間ドックに入ったところ突如、癌と宣告され、一週間後誤診であることが判明した。抱き合って喜ぶ家族たちを、私は別世界の光景のようにボンヤリ見ていた。
癌だと告知されたときから誤診とわかったそのときまでの一週間、私はトコトン考えた。
俺の人生って、いったい何だったのだろう、と。
私は学生時代哲学にかぶれていた。
三〇年前、私は生きる意味について考え、何もかもわからなくなった後に、フッと「真理の探究」にこそ生きる唯一の意味があると考え、哲学をしょうと思った。
だが、親の大反対にあってそれをあきらめたのだ。
親は「哲学をしたら死んでやる」とまで言った。私は哲学の大学院への道をあきらめ、親の経営する小さな会社に入った。
しばらくは、納得できない気持ちが残った。
だが、「これでいいんだ」と自分に言い聞かせながら、一〇年経ち二〇年経つうちに、哲学への情熱は忘れ去ってしまった。
いまは日に何回も自分に「これでいいのか」と問い返している。
そして、冷や汗とともに「よくない」と答えている。
会社は健在である。
家族も健在である。
しかし、それは真の意味で「自分のもの」ではない。
「自分のもの」は何も残っていない。
このまま死んでしまうとしたら、なんと虚しいことか?
まさにそう三〇年前の自分は内心激しく叫んで哲学をしようとしたのではないか?
青春ははるかかなたに去ってしまった。
もう自分に残された時間はあまりない。
これからどう生きていけばいいのか?
このまま自分の人生は失敗だったとみずからを裁いて死ぬしかないのか?
ここに登場してくる四人は、仕事に生きがいを見いだせない二十代、三十代、四十代、五十代の代表者である。
私はいままでこういう人に多く会ってきたが、じつは彼らは何よりも私自身の分身なのだ。
私はたまたま三七歳にしてはじめて定職を得たが、それはほんとうに偶然的なことであり、いまだに自分にとって仕事とは身体にシックリこない着物を着せられているようなもの、たいそう着心地が悪い。
彼らの眩きは私の咳きであり、とはいえ多少境遇の異なった仮想的私の咳きである。
だから、以下の彼らとの談話は一種のモノローグのようなものであり、こうしたモノローグを通じて、私は私の分身にきわめて近い人々にメッセージを送りたいだけである。
ということは、本書は私と異なった感受性をもつ膨大な数の人には何も訴えることがないのかもしれない。
それでいいのだ。そうした一人であるあなたは、この本を読む必要はない。
さようなら。またいっか、どこかでお会いしましょう。
|