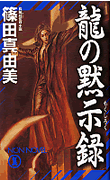 |
||||||
|
龍の黙示録
|
||||||
|
著者
|
篠田真由美 | |||||
|
出版社
|
祥伝社 | |||||
|
定価
|
本体価格 876円+税 | |||||
|
第一刷発行
|
2001/4/10 | |||||
|
|
ISBN4−396−20711−5 | |||||
|
|||||||
|
雷神の宴する夜 1 キリスト紀元二〇〇〇年五月十八日、深夜。 およそ八百年の昔、日本で初めて京都公家政権の支配に抗し、武士による政府が開かれた街は、いまは首都東京から電車で一時間の、波静かな相模湾に面する地方都市である。 だが、鎌倉の夜は暗い。 鎌倉という地名の由来は、一説によれば『屍蔵』だという。 道の隈々を巡り歩いてそのおびただしい数を数えれば、確かに屍の蔵と呼ばれても不思議はないと思われるだろう。 西から列島に沿って昇る春の嵐が、街の空をどす黒い雷雲で包んでいる。 市の北部。 南、由比ヶ浜海岸に向かって開け、平地に乏しく、市街地のすぐ裏まで切り立つ山の斜面が迫る、しかもその山が手のひらを広げたように、複雑に入り組んでいるのが鎌倉という土地の特徴だ。 見るからに古めかしい西洋館は、分岐する細い道の行き止まり、つまり指のまたの一番奥に、左右を高い尾根に守られている。 窓から目を上げればかすかな夜明かりに、新緑の広葉樹に覆われた山並みが、風にあおられて巨大な生き物のように湧き立ち、うごめき、のたうっているのが見える。 墨色の群雲を引き裂く白い亀裂。ほとんど間を置かず、小太鼓を打ち鳴らすに似た雷鳴が響いてくる。まだいくらか遠い、と思う間もなく、次の光が走る。 裏手の山に落ちたのか、雷鳴は鈍くどおんと地を震わせた。 「近いな……」 椅子のかたわらにはサイドテーブル。その上に栓を抜かれたワインのボトルと、細い脚をしたグラスが一客。 背もたれの高い藤椅子に足を組んでゆったりとかけた、男の身なりに格別の不思議はない。 濡れたような漆黒のやや長い髪をうなじでひとつに結んだ、眉は濃く、鼻筋のくっきりと高い端正な容貌だ。 「−ああ、近い。どんどんこちらへ向かって来るようだ……」 雷霆の轟きに、窓のガラスがびりびりと振動した。 酒の滴に濡れた、かたちのよい唇もまた赤い。だがそれを飲み下す喉、少し伸びたセーターの襟元から覗く鎖骨の窪みは、雪花石膏を彫り刻んだかのように、白い。 唯一古代エジプト人だけは、雷と嵐をオシリスを倒した悪神セトと結びつけたというが、我々のファラオの民に対する知識は依然限られている。 時ならぬ嵐と稲妻に酔っての独り言なのか、それとも窓からの光の届かぬところに誰か、彼のことばに耳傾ける者がいるのか、それはわからない。 そのガラスが吹き寄せる風に打たれて、危うげなきしみを上げ出している。 しかし男はそんな危険に気づいていないのか、あるいはなんとも思わないのか。 「罪人は雷に打たれて死ぬ、あるいは落雷によって死んだ人間は罪人である。そんな俗説が西欧世界にはある。だから罪の意識を隠し持っている者は、雷を恐れる。 雷を恐れるのは真に罪ある者ではない。己れはあるいは知らぬまま罪を犯しているのではないかと、自らを責める哀れに心義しき者らだ。 大革命前夜のバスチィーユに収監されていたサド侯爵が創造した、ジュリエットとジュスティーヌというふたりの姉妹を知っている? たくましき悪女たる姉ジュリエットと、心やさしき犠牲者妹のジュスティーヌ。ジユリエットは嬉々として悪徳に身を染め、無力なジュスティーヌはどこまでも虐げられて、だがいずこからも救いは現れず、すすり泣くばかり。 だけど私はいつも頭の中で、彼女たちをごっちゃにしてしまうんだ。 そしてときどきは、凌辱されるジュスティーヌこそ、加害者たちを操っているように思えるものね。 彼が口を閉ざすと、どこからか風に乗って、怯えた犬の吠え声のようなものが、切れ切れに聞こえてくる。 土地のことばでいう谷、道も行き止まりの、山襲に左右を囲まれた楔形の敷地なのだ。 それが合図のようにふたたびひらめいた稲光を、床の上からはじき返したのは一振りの短剣だ。 男の視線が向けられたことを、そのどす黒いものは明らかに感知していた。 緑が細かく波を打ち、今度は丸く膨れ上がって、短剣の刃を柄まで登ってはのたうち、なにかの形を取ろうとしてはまた崩れる。 「そう、君の苦しさはとてもよくわかる。飢えているのだろう。私の匂いを嗅いで、なおのこと苦しくてならないだろう。身内から飢餓が獣のように君を噛んで、他のことはなにも考えられない。よくわかるよ。 かつては私もそんなふうだったからね」酒に濡れた男の唇が、微笑のかたちにほころびる。白い前歯がわずかに覗く。しかしそれはどこか、人の背筋を冷たくするような笑みだ。 もしも出会い方が違っていたら、私たちは敵ではなかったかもしれない。わかるかな。私が心からそう思っていることを、信じてもらえるかな?」 猫が人の話し声に耳を傾けるときのように、短剣に縫い止められた不定形の影は、いっときもがくことを止めていた。しかし彼のことばが理解されたかどうかは、わからない。 水の流れるようになめらかな、音ひとつ立てない動きだ。その手にすでにワイングラスはない。彼は空の左手を開き、どこか手品師を思わせる身振りで顔の横へとかざした。それからその手を口元へと持っていき、人差し指の腹に白い前歯を突き立てた。狭からぬ部屋の内に、突然香りの花が開いた。 シャトーの蔵で熟成を重ねた特級ヴィンテージのコルクを抜けば、あるいはその香気は、かくあたりに満ちるだろうか。 香りはまさしくその手から、皮膚の上を流れる赤い液体から立ち昇っていた。 短剣の刃によって床に縫い止められたまま、じっと男を窺っていた不定形の影。 その目は男の手から流れる血を凝視し、その芳香をむさぼり、アメーバ状の体は狂ったように身悶え、引き止めていた短剣をついに振り切った。飛んだ。 宙を飛んでくる黒い影に向かって。 五本の白い指が影に食い込み、握りしめる。指の間からもがき出た影が、ふたたび口のかたちにぐあっと開いた。声にならぬおめきのようなものが、そこから立ち昇る。 床の上を眺めても、ただ古びた短剣が一振りころがっているばかりだ。そして男が自ら傷つけた左手の指に、グラスの酒に似た色あざやかな滴はすでに乾きかけて、鉱物めいた硬質の光を放っている。男の唇が動いた。
2 窓のひとつが外から、 と音立てた。なにか大きなものが風に飛ばされてぶつかってきた、そんな音だ。 これまでガラス越しに聞いていたのとは、較べものにならぬほど大きな音を立てて、風が室内に吹き込んできた。 大人の膝ほどの高さのある窓の下枠を軽々と越えて、それはサンルームから暖炉のある居間へと走り込む。 行方を見届けて、男は窓を閉めた。グラスにもう一度ワインを満たし、それを手に居間の方へ歩いてくる。 「お帰り、ライル。そろそろ降り出したようだね」屏風の向こうにかけた声に、答えたのはウーツという獣のうなりのような、だが長く伸びた音の末は人のことばに変わった。 「−雨ならとっくに降ってるさ。ああもう、あんなにいると思わなかったから、濡れちまったよお。くそツ、気持ち悪いったら。リュウ、ソファの上のタオル取ってよ。早くっ!」 「おまえにしては珍しく手こずった、というわけか?」 今度聞こえてきたのは、少女というよりは活きの良い少年の口調だ。 それともそれはやはり、活発すぎるほどの少女が発しているのだろうか。 タオルに覆われた頭が、ひょいと屏風の端から覗く。 「そら見ろ。オレが相手にしたのは十や二十じゃきかないぜ。一匹二匹で文句いうなよ」 「あたりまえだろッ。この嵐の中で、これ以上立ち回りさせられるのはオレだって御免だからね。まとめて明月川に叩き込んでやったさ。あのまま海まで流されて、波にさらわれて太平洋の底まで行つちまやあいいんだ!」 「リュウったらまだいってる。二百年も前のこと、しつつこいつたらありゃしない」 酒を満たしたグラスを差し出すと、 だが少女にしろ少年にしろ、その大きすぎる目の輝きはあまりに野性的で人間離れしていた。 つんと上を向いた小さな鼻を宙にくんくんと鳴らして、「怪我、したの?」グラスをもぎ取りながら覗き込もうとするのに、 「本当になんでもないのさ。ただ、あの飢えたやつを見ていたら哀れでならなくなってね。そんなに欲しがっているものを、葬る前に匂いだけでも嗅がせてやりたくなったんだよ」 「の、つもりだがね」
|
|||||||
