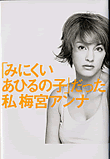 |
||||||
|
「みにくいあひるの子」だった
私
|
||||||
|
著者
|
梅宮アンナ | |||||
|
出版社
|
講談社 | |||||
|
定価
|
本体価格 1300円+税 | |||||
|
第一刷発行
|
2001/3/11 | |||||
|
|
ISBN4−06−210665−5 | |||||
|
それからあとは、ますますつらい日がつづきました。あひるたちはよってたかって、あわれなあひるの子をおいだそうとしました。 ─ アンデルセン 『みにくいあひるの子』より
あっ、私はみんなと違うんだ。 小学校に入学したとたん、私は自分の顔が大嫌いになってしまった。自分の顔の造作がほかのみんなと違っていることに最初に気づいたのは、小学校入学時に撮った集合写真を見たとき。 みんながそれぞれに違った私服を着ていたからだろうか、幼稚園に通っていたころは、そんなことは思ってもみなかったのに。 私立の女子校に入って、全員が同じ制服を着せられたとたん、集団の中で私の顔だけがポカッと浮き上がって見えた。 少なくとも自分にはそう見えて、それがとてもショックだった。これが、自分の顔だちがほかのみんなとは違っていることに最初に気づいた瞬間で、それはとてもいやな体験だった。 モデルの職業につくまで、写真はもちろん、鏡、ショーウィンドウなど、自分の顔が映るものはなんでも嫌い、ずっと見るのを避けていた。だから、私の学生時代の写真は極端に少ない。それにもう一つ、いやでたまらなかったのが、「アンナ」という奇妙な名前。 私の年代でもまだ、女の子は終わりに「子」のつく名前が多く、「小百合」とか「明美」とか、「子」がっかない人もいたけれど、自分の名前だけがとびきりヘンで、なぜ「子」がっかないんだろうとしきりに悩んでいた。 「アンナ子」ではおかしいし……おまけにカタカナ。教室で作文を読まされるときなど、題名のあと、「何年何組、梅宮アンナ」という、その「アンナ」が口からスムーズに出てこず、ついモグモグと口ごもってしまう。 そのころは、自分の名前を口にするのもいやだった。母がアメリカ人だというのもすごくいやだったけど、顔がいやだ、名前がいやだということは、親には言えない。 子ども心にも、それは言ってはいけないこと、それを言ったら親を傷つけること、その存在を否定することになると、それとなく自覚していたみたい。 それだけに、よけいに自分の中に抱え込むことになり、私は顔と名前の二重のコンプレックスにさいなまれていた。 自分の顔がみんなと違うことに気づくと、いつでも、どこでも、他人からジロジロと見られているような気がしてならない。それはもう自分の顔をなめられているような、じつにいや−な気持ちだ。 当時の自分の登下校の様子で思い出すのは、下を向いて逃げるように早足で歩く姿ばかり。参宮橋駅から自宅まで徒歩で十五分の道すがら、必ずいじめっ子に遭遇する。 私が帰宅するのを待ちかまえていて、「ヤーイ、外人、外人」とはやしたてては、ときには石をぶつけたりする。それを避けるため、さらにずっと遠まわりして帰らなければならなかった。小学校から中学校を卒業するまで、私はなに一つ自分に自信のもてない日々を送っていた。
|
|||