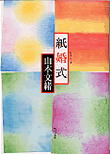 |
||||||
|
紙婚式
|
||||||
|
著者
|
山本文緒 | |||||
|
出版社
|
角川文庫 / 角川書店 | |||||
|
定価
|
本体価格 533円+税 | |||||
|
第一刷発行
|
2001/2/25 | |||||
|
|
ISBN4−04−197009−1 | |||||
|
一緒に暮らしてして十年、小結麗なマンションに住み、互いの生活に干渉せず、家計も完全に別々、という夫と妻。 傍目には羨ましがられるような二人の関係は、夫の何気ない一言で裂けた。 一緒にいるのに満たされない、変化のない日常となってしまった結婚のやるせなさ、微かな絆に求めてしまう、そら恐ろしさ。 表題作「紙婚式」ほか、結婚のなかで手さぐりあう男女の繊細な心の彩を描いた、新直木賞作家の珠玉短編集。 |
|||
|
土下座 自分でまいた種とはいえ、僕は妻が恐ろしかった。知り合ったばかりの頃、妻の祐実は屈託のない柔らかな少女だった。二十歳だった彼女は、成人式のための大振り袖を着て、背筋を伸ばして居酒屋の座敷に座っていた。僕は彼女のことを知っていた。といっても、学校の大教室や学食の中でよく見かけるだけで、言葉を交わしたことはなかった。玉子色の地に朱鷺色の模様が入った着物を着た彼女は、マシュマロのようにふっくらしていて、持って帰ってテレビの上に飾りたいほど可愛らしかった。 僕もその日成人式を迎えたのだが、田舎に帰ろうという気にはなれず、アルバイト先の居酒屋でせっせとビールを運んでいた。今日は成人式の流れで着物の客が来るだろうから気をつけろよ、と開店の時に店長が言っていたのを思い出した。そして彼は独り言のように咳いた。去年だったかな、五十万だかする着物に肉じゃがぶちまげた馬鹿がいたよなあ。あいつ、どうしたっけ。車売って弁償したんだっけ。狭い座敷は満員だった。彼女の他にも振り袖姿の女の子が数人見える。 普段なら、はいはいすいませんよとサラリーマンの尻を蹴って通って行くのだけれど、今日はそうもいかない。僕は右手に持った大ジョッキ二個と、左手のキムチの鉢を落とさないよう指に力を入れた。マジュマロ姫の後ろを通る。彼女の横顔が笑っているのをちらりと見る。今ここで転んだら、どうなるだろうとふと思った。その時後ろから「お一い、そのビールこっちだぞう」と酔っぱらいの声がした。え?と僕は振り返った。その拍子にビールのジョッキが何かに当たった。 「きゃっ」と悲鳴が上がる。斜めになったジョッキから、彼女の結い上げた髪にビールがこぼれたのだ。しまった、と思ったとたん、僕はパニックに陥った。左手からつるりとキムチの鉢が落ちる。それは猫のように空中で回転し、彼女の正座した膝に、ぼとんと落ちた。あの時でさえ、彼女は怒らなかった。僕はマンションのドアの前に立っている。この鉄のドアを僕は今まで何度開げただろう。開ける度に、少しずつそれは重くなっていくような気がする。最近はよほど覚悟を決めないと、僕は扉が開けられないのだ。もう時間は深夜一時を回っている。明日も七時に起きて会社に行かなければならない。早く布団に入って眠りたい。 けれど、僕はドアの前につっ立って自分の革靴の爪先を見つめていた。ドアの中からかすかにテレビの音が聞こえてくる。妻はまだ起きて、僕の帰りを待っているのだ。ひとつ息を吐き、ポケットから鍵を取り出してドアのロックをはずした。「おかえりなさい」と扉を開けたとたんに、廊下の向こうから妻が小走りにやって来た。「飲んでるの?」「うん。ちょっと、付き合いで」僕は言葉尻を濁して靴を脱ぐ。「何か食べる?お風呂先に入る?」妻はまるで新婚コントのように、僕が帰って来ると「ご飯にする?お風呂にする?」と必ず聞くの、だ。「いや、宴会でだいぶ食べたし、こんな時間に風呂使ったら下の階の人に迷惑だから」すがるような黒い瞳が僕を見上げている。 もう夜中だというのに彼女は化粧をして、きちんとしたシャツとスカートを身に着けていた。僕はおどおどと目をそらす。「じゃあお茶、潰れるわね」しゅんと肩を落として妻はそう言った。本当はお茶も辞退して、すぐにでも布団にもぐり込みたかったが、いくら何でもそこまですげなくするわけにはいかない。キッチンに向かう妻の背中を見送ってから、僕は寝室に入った。寝室といっても和室に布団を敷いて寝ているだけだ。今日もそこに、二組の布団が並べて敷いてあった。 結婚する時に母親が贈ってくれた、赤と青の羽毛布団が白いカバーを掛けられて今日もぴったり寄り添うように並べられている。妻は最初、和室に布団を敷いて眠ることに反対した。頂いた布団はお客様用に取っておいて、洋間にベッドを二つ置いて寝室にしましようよと主張したのだ。僕はその時「ダブルベッドならいいよ」と冗談まじりに言った。その時の妻の表情を、僕は一生忘れないだろう。まるで色情狂を見るような目で僕を見たのだ。いたく傷ついた僕は、妻がリビングで寝ようが台所で寝ようが絶対和室で寝てやると決めた。 しかし今ではこう思う。あの時ダブルベッドにしないで本当によかったと。枕元にきちんと畳まれてあった。バジャマを着て、僕はリビングに戻った。湯気をたてたお茶が二つと、微笑んだ妻が待っていた。ソファに座って僕はテレビのリモコンを取り上げスイッチを入れた。深夜の、バラエティー番組が画面に現れる。「ねえ、今度の土曜日はお休み?」祐実が僕に尋ねる。僕は彼女の方を見た。ソファはテレビの正面に置いてあって、僕と妻は並んで腰掛けている。 なのに僕の目に入ったのは彼女の横顔ではなかった。彼女は上半身をひねって、正面から僕を見据えていた。「……し、仕事なんだ」思わず僕は口ごもる。「そうなの。それじゃ、仕方ないわね」「ごめんな」「いいの。でも日曜日はお休みなんでしょう?」瞳昧に頷いて僕はチャンネルを切り換えた。妻はテレビにちらりとも顔を向けない。左頬に痛いほど視線を感じる。毎日帰って来るのは深夜で、それも間違いなく酒が入っていて、土曜日は仕事と称してどこかに出掛けて行き、日曜日は疲れたと言って一日中寝ている。 そんな僕に妻は一言も文句を言わなかった。文句どころか、こうして笑顔で尽くしてくれるのだ。例のキムチ落下事件から約七年、僕達は言い争いというものをしたことがなかった。険悪な雰囲気になったことがない、というわけではない。僕は気に入らないことがあると黙ってしまうし、妻も怒っていればいるほどそれを口に出したりはしなかった。「ねえ、お願いがあるんだけど」妻のその一言に心臓が飛び跳ねた。けれど僕は冷静を装ってお茶を飲んだ。 「日曜日の午後、もしよかったら車を出してくれないかしら。お米とかお味噌とか、重い物を買いたいの。スーパーまで行ってくれると嬉しいんだけど。でも、あんまり疲れていたらいいわ。自転車で行くから」柔らかく言って祐実は笑った。ああ、これはもう、すごく怒っている。「もちろんいいよ。さ、寝ようかな。明日も早いし」僕も妻に合わせて明るく笑った。寝よう寝よう、と空笑いをしながら洗面所に向かおうとした僕の背中に彼女が言った。 「県道沿いに、大きな家具屋さんがオープンしたの知ってる?」唐突な発言に僕は振り返る。「え?」「チラシが来てたの。ほら見て」祐実は楽しそうに広告をひらひら振ってみせた。「開店記念セールだって。まあ、ベッドもこんなに安いわ。あなた、前にダブルベッドが欲しいって言ってなかった?」ほがらかな妻の声を聞きながら僕は逃げるように洗面所に向かった。鼓動が速い。鏡に向かいコップに立てかけてある歯ブラシを手に取ると、その手が震えていた。 そして震えた歯ブラシの先に、何か緑色のものがなすり付けてあることに気がついた。匂いを嗅ぐと、つんと鼻を刺激した。舐めてみるまでもない。いつも歯磨き粉を置いてある場所に、練りわさびのチューブが置いてあった。僕は祐実に、ぞっこんだった。お願いしてお願いして、土下座して、結婚してもらったのだ。二十歳だった祐実。美しい着物の膝に大盛りのキムチをぶちまけられた彼女は、ゆっくりと立ち上がった。まわりの人が慌てて渡したおしぼりで拭いてはみたが、無残にもオレンジ色の染みが大きく咲いていた。事の重大さに声も出せずにいた僕に、彼女は静かに微笑んだのだ。こんな格好でお酒を飲みに来る私が悪いんですから。一言そう言い残し、彼女は優雅に草履を履いて店を出て行った。 僕と彼女の連れの数人は、急いで彼女を追いかけた。しかし彼女はちょうど通りかかったタクジーをひらりと手を挙げて停め、大騒ぎをする僕達の前から鮮やかに去って行った。だからといって、そのまま僕が無罪放免になっていいわけがない。僕は翌日、ありったけの現金と菓子折りを持って彼女の家を訪ねた。人生最初の土下座である。許してもらおうとは思っていなかった。いっぺんには無理でも、、バイトを増やして少しずつ弁償するつもりでいた。なのに彼女と彼女の母親は私を家の中に招き入れ、お茶まで出してくれた。染み抜きすれば大丈夫ですし、汚れたら困る格好で居酒屋に行く私の方が悪いのですから。もしそんなに気にして頂けるのなら、染み抜き代だけ頂戴します、と彼女はえくぼをつくって言った。 僕には彼女がマリア様に見えた。大袈裟なのは承知だが、でも本当にそう思えたのだ。その事件がもとで、僕と彼女は親しく口をきくようになった。学校の中で顔を合わせると、少し立ち話をする。そういうことが重なるとだんだん共通の友人というものができてきて、僕と彼女は大勢で飲みに出たりスキー旅行にも行くようになった。僕は祐実が好きだった。まるで巫女にかしずくように僕は彼女に心酔した。いつでもふんわりと笑い、言葉を荒らげたり皮肉を言ったりすることが決してなかった。 誰かが咳をすると「風邪?」と小首を傾げて聞いた。学校の中で見かける彼女は、いつも大勢の友人に囲まれて楽しそうに笑っていた。思い出すだけで胸が詰まった。あの頃のままの彼女でいさせてあげたかった。できれば僕は、死ぬまで錯覚という曇りガラスを通して彼女を見ていたかった。僕の父親が他界したのは、就職をして二年目の夏だった。母親から「死んだらしい」という電話が僕のところに入って、慌てて父親の奥さんに問い合わせた。 すると昨夜、脳溢血で亡くなりましたと告げられた。父と母は僕が高校に上がる年に離婚し、あっという間にそれぞれ別の所帯を持ったのだ。僕は父と母のどちらに引き取られるのも気が重かったので、母の新しい所帯の近くにアパートを借りてもらって住んでいた。けれど、新しい配偶者に尽くす自分の親というものを見たくなくて、僕はどちらの家にも上がり込んだことはなかった。用がなければ連絡もろくに取らなかった。 しかし、思い出したように父と母、両方から電話がかかってきた。特に何だというわけではない。世間話を少しして切るだけだ。そしてもう片方から電話がかかってくると、僕は父の、あるいは母の近況をかいつまんで話してやった。離婚した夫婦は、お互いのことになど興味がないのかと思っていたら、元気でやっていることぐらいは知りたいようなのだ。あんなに憎みあって、茶碗も鍋も投げつけあって喧嘩別れをした二人なのに、不思議なものだなと僕は思っていた。 そういうわけで、僕はずっと父と母の中継地点として使われてきた。父の死亡も、母がどこからか噂を聞き僕に確かめさせたというわけだ。父の新しい(もうそんなに新しくはないが)奥さんは、お線香をあげに来て下さいと言ってくれたが、母は通夜にも葬式にも顔を出さなかった。僕は一応血が繋がった実の父の葬式なので火葬場まで行った。火葬場の待合室で父が焼き上がるのを出洞らしのお茶を飲んで待っている時、父の弁護士という人が話しかけてきた。遺言状もなかったので、遺産の分割は法律通りでいいかと彼は僕に聞いた。僕はきょとんと彼の顔を見つめてしまった。父に遺産があることも、それを僕がいくらか貰える権利があることも考えもしなかったのだ。どうせ貰えても大した金額じゃないだろう。 当てにすると後で落胆するので、僕はなるべくそのことは考えないようにして過ごすことにした。そして、そんなことがあったことも忘れかけていた一年後、しょっちゅうマイナス残高になってしまう淋しい僕の通帳に、三千万円の入金があった。銀行のキャッシュコーナーで腰を抜かした僕は、そういえばまだ子供の頃、酔っぱらった父が裏のお山は俺のもんだと言っていたのを思い出した。二流の私立大学を出て、コネも能力も何も持っていなかった僕は、受けた会社をことごとく落とされて最後に小さなゲームソフトの会社に拾ってもらえた。 そこで営業部に配属されたが、忙しいわりには驚くほど少ない給料しか貰えなかった。だからといって、どこにも文句のぶつけようはない。その会社しか僕に給料をくれるところはなかったのだから、世の中を責めるより先に自分の無能さを責めなければならないだろう。その頃の唯一の楽しみといえば、一ヵ月に一度ほどの割合で祐実と食事をすることだった。どうも彼女にはステディな相手がいる様子だったが、それはそれで構わなかった。もちろん失恋であるからそりゃつらかったが、たまに親しい友人として会うことができる方が僕には大切なことだった。何よりも恐いのは、彼女に会えなくなってしまうことだった。それに僕には己というものが分かっていた。何をやらせても中の下で、かといって素晴らしい人格者というわげでもない。 趣味もなく、野望もなく、金もない。ただひとつだけ漠然とした夢があるとしたら、それは祐実に求婚することだった。うちの会社は小さな会社なので、努力次第では若いうちに幹部になれる。もしも出世できる見通しがたち、彼女がまだ独身であればプロポーズしてみよう、僕はそう思っていた。しかしそれは本当に夢の夢だった。怒鳴られてばかりの役立たずな僕が、役付きになどなれるわけがない。それに、世の中の男達が彼女を放っておくわけがなかった。彼女は年々美しくなる。 相手を包み込むような笑顔は変わらないが、子供じみていた仕種が会う度に大人のものになっていった。彼女には僕ではなく、もっと相応しい男がいるだろう。そんなふうに、まだ五十年以上もあるかもしれない自分の人生も、目の前に座っている惚れた女性も諦めかけていた矢先に三千万円の収入である。
|
|||