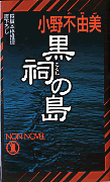 |
||||||
|
黒祠の島
|
||||||
|
著者
|
小野不由美 | |||||
|
出版社
|
祥伝社 | |||||
|
定価
|
本体価格 886円+税 | |||||
|
|
ISBN4−396−20708−5 | |||||
|
その島は風車と風鈴に盗れ、余所者には誰も本当のことを話さなかった作家葛木志保が自宅の鍵を預け失除した。 パートナーの式部剛は、過去を切り捨てたような彼女の履歴を辿り、「夜叉島」という名前に行き着いた。 だが、島は明治以来の国家神道から外れた「黒祠の島」だった…。 そして、嵐の夜、神社の樹に逆さ礫にされた全裸女性死体が発見されていた…。 島民の白い眼と非協力の下、浮上する因習に満ちた孤島連続殺人の真相とは?実力派が満を持して放つ初の本格推理!
|
|||
|
一章 1 その島は古名を夜叉島と言う。九州北西部に位置する変哲もない島で、「夜叉」と一見禍々しい名も、島にある火山を夜叉岳と称したことに因んでいるにすぎない。火山を鬼神に喩えることは決して珍しいことではないし、そこには懼ればかりではなく、畏敬の念もまた含まれている。事実、この夜叉岳は古来、近辺を航海する海上民からは尊崇を受けていた。航行標識の未整備だった時代においては、海上に勃然として聳える標高四百メートルの山は恰好の目標物だったからである。だが、その名も地図の上から消えて久しい。島が消失したわけでは、勿論ない。時代の趨勢に従って無害で凡庸な名に書き換えられてしまったのである。 「─島?」陽灼けした顔に深い笑い皺を刻んだ老人は、その凡庸な名を繰り返した。「そりゃあ、夜叉島のことだろう。いいや、この辺じゃあ、そんな名前で呼ぶ奴アいねえよ。夜叉島、でなけりゃ御岳さんだ」老人は言って、車窓から見える海に目をやった。路線バスの座席シートは、もとの藍色が陽に均一て、海と同じ藍鼠に退色していた。「島に火山があってね、夜叉岳と言うんだが、それを御岳さんとも呼ぶんだよ。ああいう目印になる…ってのは、漁師にとつちゃあ守り神みたいなもんだからね。だから漁師たちは島のことも御岳さんと呼んだりするよ」バスが行く国道沿いに長く防波堤が続いていた。その向こうには海を隔て、墨色に岬が延びている。 防波堤から岬へと弓なりに続く海岸では、黒い岩礁が累々と折り重なって磯を作っていた。その沖合を探してみても島の影はない。老人は車窓から入る光に目を細めながら笑った。「いんや、こっから島は見えないよ。山の反対側になるからね。この先の港でバスを降りりゃあ、島に行く船が出てる。そうだな、島まで渡船なら五十分ってとこかね。名ばかりのフェリーもあるが一往復しかしないし、時間も倍はかかるね。渡船なら日に三便だが、この時間じゃ夕方の便まで、かなり待つことになるよ」老人の横顔を照らす強い陽脚は、残暑の色も腿せている。「うん、島にある港は一つだけだ。集落が一つしかないんだよ。 もともと夜叉島ってのは、上島と下島の二つでできててね。とは言っても、陸続きなんだが。そうだな、ひょっとしたら大昔にゃ別々の島だったのかもしれんね。それが夜叉岳の噴火で繋がったんだろう、そういう形をしてるよ。歪んだ瓢箪形って言うのかね。上島と下島がくびれて『く』の字の形に繋がってるのさ。上島には、でんと御岳さんが控えてる。西の麓のほうが長くて、ちょいとくびれて下島の山に繋がってるんだが、それがちょうど港を囲い込むような恰好でね。─まあ、このへんの海は荒れることが多い。台風のシーズンは勿論だが、冬から春にかけても時化ることが多くてね。夜叉島はそういうとき、船が逃げ込むのに丁度いい港だったんだよ。御岳さんと下島がいい按配に風を遮ってくれるんでね。 昔はそれで重宝したようだ。うん、住んでるのはほとんど漁師たよ。今もそうたね。温泉?いいや、そんな酒落たもんはねえよ」老人は言って、快活に笑う。「最近は島興しってのが流行りでね。どこの島も知恵を絞って、名産品を作ったり観光名所を作ったり苦心惨倍してるもんだが、なにしろ夜叉島は愛想のねえ島だ。海水浴場やらキャンプ場やら作ろうたって、島のぐるりは断崖絶壁ときてる。そもそも港以外にゃ船を着ける場所もないんだ。温泉もなけりゃ洞窟もねえ。見るもんがありゃしないんだ、どうにもなるまいよ。離島振興法のおかげで港だけは立派なもんだがね。−うん、戦後にそういう法律ができて、国の助成金で島の整備をやるようになったのさ。だから港は立派だが、漁港を眺めてもしょうがないからね」、パスは海岸線に沿って大きく進路を変えようとしていた。 行く手を遮っていた山の斜面が切れて、海に向かって眺望が開けた。陽が翳ってきたのか、海の色が暗くなった。風の加減か、潮の加減か、こころなし波も立ってきたようだった。海上は靄っている。その向こうに微かに見える薄墨色の滲みを、老人は硝子越しに指差した。「あれがそうだよ、夜叉島。天気がいいと、もっとはっきり見えるんだがね。ちょっと白い煙みたいなのが見えるだろう。あれが小夜叉の噴煙さ。御岳さんの東っ側が噴火してね、そこに新しい火口ができたんだよ。いいや、最近のことじゃねえ。明治の中頃とか、ずっと前の話だ。 火口かい? そりゃあ、小夜叉に登りゃ見られるだろうが、簡単には寄りつくことができねえから。何しろ、集落の反対側になるからね。行くとなると大夜叉を越えなきゃならんが、大夜叉には道がねえんだ。海から寄りつこうにも船を寄せる岸がない。ときどき大学の先生が小夜叉の調査に来るようだけどね、そん時や漁 船を借りて近くまで行って、ゴムボートで上陸するらしいからね。いや、大夜叉のほうはもう噴煙を上げてないよ。すっかり鳴りを潜めて、今じゃ火口も埋まつちまってるって話だ」老人の言う噴煙は、そうと分かって見なければ見て取れない。そもそも島影自体が溶け消えるように薄かった。島の輪郭すら朧で、どこか幻めいている。 「火口見物さえできないってわけだよ。そんなふうだから大した宿もなくてね。俺の若い頃にゃ、釣り客を泊める宿が二軒ばかりあったが、今でも営業してるかどうか。第一、島の連中は偏屈でね。昔、海が時化て夜叉島に逃げ込んだ連中が、船から降ろしてもらえなかったってのは有名な話だよ。よほど荒れても島に上げちゃあくれなかったらしいからね。閉鎖的って言うのかね、とにかく余所者を嫌うのさ。島の外からの嫁取り婿取りは御法度だって話だよ。さすがに今じゃあ、そんなに煩くも言わねえんだろうが、それでも未だに長男の嫁だけは島内からでなきゃ、と言うらしいからね。そうやって島ぐるみ、みんな血縁みたいなもんだから、島の外から入ってきた人間とは肌が合わないんだろうよ。だからって別に、入り込んだ者に石を投げるってこたあねえだろうが、まず歓迎はされないね。 −ああ、ここだよ」バスは海岸沿いの道を離れ、港に面した小さなロータリーに入ろうとしていた。最寄りの駅からバスで十五分、港の外れには整えられた桟橋があり、そこには真新しい白い船が停泊していた。いかにもこぢんまりとした遊覧船ほどの船舶だった。バスの中の乗客は二人だけ、老人は隣に坐った男を促した。三十半ばの長身の男だけが立ち上がり、老人に向かって軽く頭を下げてからバスを降りた。港に人影はなく、待合所にもやはり人影がない。男がそれを確認している間に、ただ一人の乗客を乗せたバスが、ロータリーを出て岬のさらに先へと去っていく。彼はそれを見送りながら、もう一度、軽く頭を下げた。2すでに陽は傾いていこうとしていた。強い陽脚が和らいで風景に穏やかな色調を添えていたが、海がら吹き寄せる風ばかりは潮を含んで重い。 彼は人影もまばらな港の様子を一渉り見廻し、待合所の脇にある切符売場へと向かった。窓口に書かれた「夜叉島行き」という文字に目をやり、売場の中を覗き込む。ボックスじみた売り場の中では中年の女が一人、事務服に似た制服を着て所在なげに坐っていた。「済みませんが、お尋ねします」彼は声を掛け、一枚の写真を差し出した。「この写真の女性を見掛けませんでしたか」女は不審そうに写真と男を見比べた。「中央の女性ではなく、その後ろの女性ですが」「……あなたは?」失礼しました、と詫びて、彼は名刺を差し出す。−石井探偵事務所、式部剛。受け取った女は珍しいものを見るように、今度は式部と名刺とを見比べた。「あらまあ……人捜し?」式部が肯定すると、女は首に下げていた眼鏡を掛け、式部の差し出した写真に改めて目を落とした。女が首を傾げたのを見て取って、式部は口を挟む。 「中央の女性ではありません。右のほうに写っている女性です」「この人?」女は写真の端を指差した。写真は結婚披露宴のスナップで、中央にはタキシード姿の花婿と、若い女が映っていた。花嫁ではない、来客の一人だった。カメラのほうに笑顔を向け、ポーズを取った二人の背後には別の女が写り込んでいたが、肝心の二人にはピントが合わず、背景のほうにピントが合ってしまっているので、女の写りは悪くなかった。「そうです。小さくて恐縮ですが」「いつごろのこと?」「先週だと思います。それ以前ではありません」「先週、ねえ……」女は困ったように言って、それからああ、と声を上げた。 「思い出したわ。見掛けましたよ」「確かですか?」女は頷いて、椅子のすぐ背後にあるドアを開けた。奥は事務所に続いている。女は坐ったまま身体を捩ってドアの外に顔だけを突き出し、「野村さん」と、呼び掛けた。すぐに振り向いて、あの人のほうが覚えてるはずだから、と式部に言い、写真を窓口から差し出して返した。野村は女と同色の制服を着た初老の男だった。事務所のほうから待合所を抜けて出てくると、式部から名刺と写真を受け取り、すぐに「ああ、あの人」と優れた声を上げた。「覚えておいでですか」式部の問いに、野村は確信を籠めて頷いた。「あれは一日だったかな二日だったかな。どっちかだと思うんだが。船に乗ったよ、二人とも」「二人?」怪証そうに問い返す式部に頷いて、野村は写真を返した。 「連れがいたんだよ。同じくらいの年頃の女だったな。よく覚えてる」夜叉島に向かう渡船に乗るのは、大多数が島の者だった。あるいは島へ物資を運ぶ業者で、観光客はほとんどいない。たまにいたとしても釣り竿を持った年配の男女で、旅装の若い者といえば帰省してきた島の出身者に限られる。野村が見た二人の女は、ともに二十代の終わりから三十代にかけて、二人ともシャツにジーンズと、ごく砕けた旅装だったが、やはり土地の者とはどこか違う垢抜けた匂いがした。これは帰省組だな、と野村は思った。都会から戻ってきたのだろう。観光客である可能性は端から念頭にも昇らなかった。「帰省かね」と、野村は二人に声を掛けた。 野村は空き時間の片手間に、歩道を掃いているところだった。二人の女は、切符売り場の脇に据えられたベンチに並んで腰を降ろし、黙りこくっていた。「いいえ」と女のうちの一方が、驚いたように顔を上げて愛想良く答えた。「旅行かい。そりゃ珍しい」「ちょっと用があって」女は微笑んで言って、取って付けたように、「島に旅館はあるでしょうか」と尋ねた。「旅館?いいや、そんな大層なもんはないよ。民宿ならあるけどね。なんだい、宿の手配もせずに来たのかい?良かったらこっから予約を入れてやろうか」野村が言うと、女は連れを振り返った。連れのほうは煙草を御えて俯いたまま、黙って微かに首を横に振った。女は野村を見上げて笑んだ。 「結構です。ありがとうございます」「飛び込みで行っても泊まれるかどうか分からないよ。親父が片手間にやってるようなとこだからね」「泊まることになるかどうかは分からないんです。念のために訊いただけですから」「そうかい?」「多分日帰りできるでしょう。御親切に、どうも」野村は二人の足許に置かれた旅行鞄を目に止め、日帰りのつもりにしては大きな荷物だ、と思ったが、それ以上は口にしなかった。というのも、二人の様子が何となく曰くありげに思われたからだった。それは二人が陽光の中、戸外のベンチに坐っていたからかもしれない。この辺りの十月初頭はまだまだ暑い。 にもかかわらず、二人とももう長袖を着込んでいた。待合所に入れば陽脚も避けられる、クーラーもまだ入っている。なのにじっとベンチに坐っているのが、どことなく不自然に思われた。楽しい用で行くのではないだろう、と野村は思っ た。ああして並んで坐っていながら、会話をするでもない。かといって別に険悪な様子も気まずい様子もなかった。互いに黙り込んでいても苦にならない─そういう、ごく自然な近しさのようなものを感じた。同じような背恰好、雰囲気で、容貌が似ていないことを度外視すれば、姉妹なのかと思えなくもなかった。 気になってちらちら見ていると、煙草を吸っていた女のほうが野村の視線を厭うように、顔を背けて真っ黒なサングラスをかけた。野村は咎められたように感じて、その後はあえて視線を向けず、掃除を適当に切り上げると事務所に戻ったのだった。野村が二人をもう一度見たのは、乗船が始まってからだった。乗船時間が来て野村が桟橋に向かうときにも、二人はベンチで黙り込んでいた。乗船を促すアナウンスが流れると、真っ先に二人が乗船口にやってくる。野村は差し出された切符の半券を折り取りながら、 「行ってらっしゃい」と声を掛けた。これに微笑んで応じたのも、やはり先程と同じ女のほうだった。「本当に宿はいいのかい?」野村が言うと、女は先んじて船に乗り込む連れのほうを見やった。連れが振り返らなかったので、困ったように微笑む。「大丈夫だと思います。−そうですね、でも、宿の名前だけ教えてもらえると」ああ、と野村は笑った。「大江荘って言うんだよ。港を出て上島のほうに折れた先にある。もう一軒、いづみ屋って宿もあるけど、あそこはこの季節、客を泊めてねえから」「大江荘ですね。ありがとうございます」 「いいや、お気をつけて」どうも、と微笑って女は連れを追いかけ、船に乗り込んでいった。「それだけだよ」と、野村は式部に言った。「その写真の人は、煙草吸って黙りこくってたほうの女だよ、間違いない」野村が断言すると、切符売り場の中から女も同意の声を上げた。「連れの人のほうが片道の切符を二枚買ったんですよ。お捜しの人は黙って脇に立ってました」式部は頷いた。「どうやら間違いないようです。二人が乗ったのは何時の便でした?」「あれはフェリーだったから、十時の便だね」「二人が戻ってきたのを見ましたか?」 「いや。俺も気をつけてたんだが、戻ってないね。それで島に泊まったんだな、と思ったんだ。そんなことなら、こっから宿に予約を入れてやりゃあ良かったと思ってね。俺はそれきり見てないよ」「それきり─?しかし、十月一日といえば八日前、二日でも七日前ですね?」式部が問うと、ああ、と野村は当然のことのように頷いた。「そりゃあ。でも、俺にだって休みってもんがあるからね。俺の出てる日なら、船が着くたびに乗船口に付くから見落とすことはないが。瀬能さんはどうだい」言って野村が売場を振り返ると、中の女もまた首を傾げた。 「あたしも見てないわねえ。でも、あたしがお客の顔を見るのは切符を売るときだけだから。島からこっちに来た人は、このへんに寄らずにまっすぐバスに乗っちゃいますからね。そこのロータリーでバスが待ってるから」そして、その瀬能にも休みがあるわけだ、と式部は心の中で思いながら野村に向き直った。「野村さんのお休みはいつでした?」野村は首を傾げる。売場の中のカレンダーに目をやって、「先週は金曜─たから六日たな。てことはあの二人、結局、島でのんびりしたんだねえ」式部はこれには答えなかった。彼女は九月末以来、行方が知れなかった。─ 三日で戻ると言い残していったにもかかわらず。 |
|||