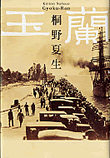 |
||||||
|
玉蘭
|
||||||
|
著者
|
桐野夏生 | |||||
|
出版社
|
朝日新聞社 | |||||
|
定価
|
本体価格 1800円+税 | |||||
|
第一刷発行
|
2001/3/1 | |||||
|
|
ISBN4−02−257583−2 | |||||
|
第一章 世界の果て 窓から射し込む月の光は、本が読めるのではないかと思えるほど眩かった。実際に本を開いてみれば、青白い光は明るいようでいて実は暗く、輝いているようでいて重く沈んでいる。黒い活字は記号の羅列にしか見えず、言葉に繋がろうとしない。果ては言葉に何か意味があったのかと疑いさえ生じる始末だった。広野有子は本を傍らに置き、枕元の照明を点けたいという誘惑と戦った。いったん点けたが最後、オレンジ色の光に頼ってしまって、スイッチを切るのにまたも覚悟が必要になるからだった。上海に来て以来、有子は不眠症に悩まされている。今夜も眠れないのではないかという不安と翌朝の気分の重さを想像して、日々憂欝さが更新されていく。 一番辛いのは、長い夜の間に湧き上がる妄想が心のあちこちに滞ることだった。妄想の中身はいつも同じだった。じりじりと焦がれるような愛しさと共に松村行生の顔が浮かび、破裂する憎しみと共に闇に消え去る。その果てしない繰り返しを朝まで堪える。このままでは狂ってしまうのではないかという恐怖が有子の目を闇の中で開かせる。有子は床がぼんやりと発光するのを感じた。リノリウム張りの床に溜まった月の光だった。見ていると自然に肩の力が抜けていった。何もしなくていいのだ。何も考えなくていいのだ。眠れないのなら、いっそ眠らずにこうして月の光を眺めていればいい。 間もなく、瞼が自然に重くなり、有子はほっとしながらようやく得られた眠りに落ちていった。その夜以来、月の光を溜めて眺めるのが有子の入眠儀式になった。夜十時過ぎ、有子は部屋の明かりを消し、何人の留学生が使ったかわからない硬い粗末な寝台に横たわる。木製の寝台は幅が狭く、寝返りを打つと冷たい漆喰の壁に顔が当たりそうになる。壁のその位置は、昼間見ると少し薄黒くなっていた。東京に住んでいた頃の有子なら我慢できないほどの不潔さだったが、今はその黒ずみさえ、自分と同じような学生がいたことを証明している気がして愛おしい。壁をそっと撫で、上海のデパートで買った薄い羽布団にくるまる。 暑い日は、ごわごわしたタオルケットを腹まで掛けた。。パンヤを詰め過ぎて張り切った枕は、いつまでたっても弾力があり、頭に馴染まない。が、それも一向に構わなかった。清潔な寝具や便利な生活雑貨に囲まれて暮らす、というつまらないことに拘って生きてきた自分が、可笑しくもあった。長い年月を経た両開きの窓の木枠は膨れて歪み、窓を完全に閉じることはできなかった。幾ら磨いても無数の細かい傷があって決して透明にはならない窓ガラス。あちこち剥がれた床のリノリウム。 だが、そんなことはお構いなしに、月の光は窓の周辺から床の隅々まで毎夜たっぷりと降り注ぐ。有子は寝台にじっと横たわり、カーテンのない窓辺を眺めて、月の光が溜まるのを辛抱強く待った。真夏の月光の色は薄く冷たく、冴え冴えとしている。しかし、夜が更けるに従って、光に温もりがあるのではないかと思えるほど濃厚に密度を増し、辺りをぎらぎらと照らし出していく。月光は溜まるものだということ、そして色や濃度を備えているのだということを、有子はここで初めて知ったのだった。やがて、三畳にも足りない小さな寮室は豊かな光に満たされ、貧相な家具も汚れた床も別のものに見えてくるから不思議だった。おそらく自分の顔も違って見えるはずだ。 有子は月光の中で手鏡を覗いた。黒い髪が闇に沈んで顔は白く浮かび、別人のように美しかった。有子は心が満たされたのを感じる。そして穏やかに寝入ることができる。雨の日は朝から何も手に付かなかった。どうやって長い夜を過ごせばいいのか心配で堪らず、夕暮れ時は気が欝いだ。が、方策はわかっていた。雨はいっか必ず上がるのだから、ひたすら待てばいいのだ。雨降りの日、有子は諦めずに空を見上げる。曇った日は、雨乞いならぬ月乞いのために窓を開け放って風向きを調べ、雲が吹き払われるのを待った。たとえ頼りない新月であろうと、ともかく月さえ出れば有子の心は安まるのだから。 有子は六月から上海のH大学に留学し、構内にある留学生のための寮で暮らしている。すでに八月半ば、ニカ月近い月日が経とうとしていた。留学生楼という名の寮は五階建てで、一応ビルディングの体裁を成してはいる。だが、改装工事の時にひょいと覗き込んで見た建物の骨格は、鉄筋ではなく太い竹が組み合わさって出来ていた。強風が吹くと建物の内部で、ひゅうひゅうと竹藪を渡る風のような音が微かに聞こえてくる。それを留学生仲間に言ったことがあるが、一笑に付されたところを見れば、有子にだけ聞こえたのだろう。寝台や机などの備品が簡素で古いせいか、あるいは扉や窓の仕様が古風なためか、ここで暮らしていると五、六十年も昔に時間が逆戻りしたかのような錯覚が起きる。 東京では必需品だった携帯電話やパソコン、CDプレーヤーやテレビなどの機器と無縁の暮らしを余儀なくされているせいもあるのだろう。が、有子は不便だと思ったことは一度もない。むしろ、縁が切れて爽快だった。その代わり、自分の心の中に何によっても埋めることができない空洞が存在している、と感じられてならないのはどうしてだろう。東京で生活していた時は気が付かなかった虚ろな穴。いや、気付かない振りをしていたのか。強風の吹く日に聞こえた竹藪を吹き渡る風の音は、建物の内部からではなく、もしかすると有子の中から聞こえてきた音なのかもしれない。再び眠れなくなったのは三日前のことだった。月光の中に、ある異物が浮かび上がった。有子は何とも言い難い違和感を感じて頭を上げ、寝台に肘を突いてそれを眺めた。 ちっぽけなものであるにも拘わらず、いつもの光を溜める儀式を邪魔された気がしたのだつた。その正体は、テーブルの端に置き捨てられた小さな花だった。玉蘭。木蓮にも似た白い厚めの花肉。すっきりと細長く、優雅な釣り鐘のような形をした可憐な花。花弁は固く閉じられているが、クチナシにそっくりな甘く強い芳香を放つ。玉蘭は夏の街角で売られていた。二つの花を細い針金で繋ぎ、襟元の第一ボタンに留められるように細工したものを、小遣いにでもするのか老女が売っているのだった。有子は一度買ってみたいと思っていたのだが、買おうと思った時は露店が見付からず、露店を見付けた時はたまたま時間にゆとりがなかったりして、どうにも買うことができない。 玉蘭には縁がないのだと諦めていた矢先、南京路の横の路地からにゅっと現れた手が有子の鼻先に玉蘭を差し出したのだった。灰色の中国襟のブラウスに黒いズボンを穿いた、見下ろすほどに小柄な老女が有子に笑いかけている。老女は舗道の一隅で、青いプラスチックバケツを逆さにして玉蘭を作って売っていた。露店とも言えない小さな商い。老女は自分の襟元に付けた玉蘭を指し示し、こうするのだと何度も有子に説明した。ひとつ、たったの五角だった。有子は玉蘭を白いブラウスの第一ボタンに留めた。 玉蘭は有子の襟元から一日中甘い匂いを発していた。有子はその日、花の匂いに少し酔ったらしい。いつもより学友たちとよく喋ったのを覚えている。そして夕方、寮に帰って来て玉蘭を外し、机の端に置いたまま忘れていたのだった。有子は寝台から抜け出し、冷たい床を裸足で歩いた。萎れた玉蘭を摘み上げる。肉厚の花弁は茶色く変色し、饐えた甘い匂いに変わっていた。中から小さな黒い蟻が這い出て来て机の上に落ちる。有子は減れたものを見た気がして立ち疎んだ。ティッシュに包んでゴミ箱に捨てたが、それでも死骸を見てしまったような嫌な気分は治まらなかった。置き忘れて気が付いたら死んでいた、そんな遣り切れなさが伴う重い心持ちだった。 ふと、自分もこうして死ぬのかもしれないと連想した。もう一度、最初から月の光を溜めなくてはならない。有子は、寝台に戻って横たわった。しかし、玉蘭の死骸と一緒にあの安らかな心は消え去ってしまったのだった。何時間、こうして待っているのだろう。有子は寝台の上に半身を起こした。最早、光を溜めて寝入るのを待つ、という長閑なことを楽しめなくなってしまった。こうなるのを一番怖れていた。心の空洞を埋めるものは、この部屋のどこにも、そして自分自身の中にも存在しなくなったのだから。どうしたらいい。 有子は両目を閉じ、それからゆっくり頭を巡らせて月光が射し込んでいるはずの窓辺を眺めた。しかし、そこに満ちているのは、豊かさの欠片もなくなった、薄ら明るい、ぼんやりとした月の光だった。有子は枕元のアルミ製の照明を点け、また横たわっては消すことを数度繰り返した。なす術がないままに、ざわざわと過去の出来事が押し寄せてくる。不安や絶望や失意。そして孤独。負の感情が有子を沈ませる。なぜ、東京の暮らしを捨ててまで上海に来たのか。書籍編集という女性にしては得難い職業や、親切で優しい友人たち。 やっと見付けた居心地の良い便利な部屋。気の置けないレストラン。何年間も努力して手に入れたもの、実らせたものを捨ててまで見知らぬ土地にやって来たのはなぜか。明るい陽光の下では幾らでも理由を述べることができるが、この夜の闇の中では、たった一人でその答えと対侍しなくてはならなかった。有子は辛くなり、思わず小さな叫び声を上げた。「助けて!」部屋はしんと静まり返っている。いつもなら月の光が心を満たしてくれるのに、三日前から玉蘭がそれを邪魔している。玉蘭など買わなければ良かった。有子は自分の心が突然挫けた理由がわからない。他人より脆弱なのか。情けなさより、自分自身に対する憎悪が湧いてくる。 有子は部屋の隅の暗がりに向かって言葉を投げ付けた。「私は馬鹿だ」そう言った後、有子は口を歪めた。鏡を見たら、きっと嗤っているようにも見えたことだろう。故郷の小さな町では、有子は優等生で有名な存在だった。中学・高校は進学校に通い、成績はいつも上位。学校でも近所でも評判良く、何事もそつなくこなしてきた自分。利口で、そこそこの美貌にも恵まれている。東京の大学に入った時、有子は初めて不眠症になった。東京には無数の「広野有子」が存在しているという事実に打ちのめされたからだった。 そればかりか、自分を遥かに上回る女も多数いる。その事実を何とか認め、咀嚼するまでの数年間は苦痛に満ちていた。自分と同程度の女が沢山いるのなら、更に上の「広野有子」を目指すことでしか勝ち残ることができないではないか。有子は成績を上げることに腐心し、必死に優の数を増やしていった。大学でも優等生になった時、有子はようやく達成感を得ることができた。不眠症は嘘のように治った。それは他人に評価されるところでしか存在し得ない達成感だった。だとすれば、永遠に誰かの評価を待たなくてはならない。きっと何かが間違っているのだ。そんな間違いに気付いた自分は決して馬鹿ではないはず。ならば、松村行生と別れたことが馬鹿な行いだったのか。そこまで考えた有子は、違う、と激しく首を振った。「違う。行生は関係ない。私は新しい世界で何かを始めたかったのだ。 新しく生まれ変わりたかったのだ」何を始めたかったというのだろうか。中国語か。有子は大学で単位を取っている中国語初級講座の授業を思い出す。張り切って予習にいそしんでいたのは、留学が決まって準備していた頃だった。実際に上海に到着してみると、あらかじめ勉強していた言葉はほとんど通じず、買い物で使う程度の日常会話を繰り返すだけの日々となってしまった。どんなに焦っても、三十歳になった途端、頭は錆び付いて十代の頃の暗記力などもう持ち得ない。言葉というものは、何かを表したいと願う強い気持ちがなければ、上達もしなければ、何の意味もなさないのだということにも 気付き始めていた。ここにいて、中国語の初級をマスターしたところで何が待っているのだろう。上級への果てしないステップアップ、それしかない。 だったら、東京でしてきたことと同じではないか。いや、これまでの自分の人生と同じだ。有子は自分が選び取ってきた選択のすべてが、そしてそのための努力が虚しくてならない。有子は大きな溜息を吐いた。「ここは新しい世界なのか」突然、男の張りのある声が響いた。頭の中にいきなり話しかけられた気がして、有子は思わず答えた。「そりゃ、そうよ」撫然とした自分の声が空疎な部屋に響き渡った後、有子はたった一人で部屋にいるのだという事実を思い出し、ぞくっとした。鳥肌が立つ。 今、確かに会話をした。誰がこの部屋にいるのだろう。やがて、有子は寝台の裾に男がいるのに気付いた。男は黒っぽい服を着て椅子にでも腰掛けているのか、月光の中に上半身をほんのりと浮かび上がらせている。そんなところに椅子などない。有子は痺れるような恐怖を感じ、困ったことになったとぼんやり考えていた。「ここは新しい世界なのか」男はもう一度同じことを聞いた。今度は声の振動に伴って部屋の空気が微かに共鳴するのがわかった。性格の烈しさを感じさせる、子音のはっきりした低い声だった。男は、確実にこの部屋に存在していた。「僕にとってはどこだって、初めて来た場所は世界の果てであることは間違いなかった。 新しい場所に来たから、新しい世界が始まるなんて幻想だ。新しい場所に足を踏み入れるってことは、良く知っている世界の、実は最果ての地に今いるっていうことなんだ。違うかな」男が、有子の顎の辺りを眺めながら早口に喋っていた。男のやや伝法な口調が有子の恐怖を和らげた。「私が世界の果てにいるって言うの」「そう。新しい世界で、新しい生活が始まるなんて幻想だ。これまでのすべてを引きずって、あんたの世界の最果ての場所に来たんだ」有子はいきなり現れた見知らぬ男と会話している不思議さも忘れ、窓辺を振り返った。月光は変わらず降り注いでいる。外は暗闇。世界の果てにいる、と言われた寂しさが有子を襲っていた。 「どうしたら戻れるのかしら」「戻りたい?どこに」男は苛立ったように舌打ちした。「だって、果てにいるよりは真ん中に戻りたいもの。果てにいるのなら、落っこちてしまうかもしれない」男は笑った。「果てに来てしまったと思ったら、どんどん知らない場所に行けばいいんだよ。それが最果ての最前線になるだろうさ。船乗りは皆、そう思う」「船乗りなんですか」「そうだよ」「あなたは誰ですか」この問いを発した時すでに、有子は男が幽霊であることを承知していた。ここに人間が居るのだとしたら、物の怪であることは間違いない。 しかし、もう恐怖は感じない。今の有子にとって一番怖いのは、向き合わなくてはならない自分の心の虚ろの方だったからだ。「あんたの良く知っている人間だよ」男は笑いを含んだ声で答えた。それなら、松村行生しかいない。だが、行生とは東京で別れて来たばかりだ。それに男が行生であるはずがない。顔も声も何もかもが違う。不意に、今すぐ行生に会いたいという痺れるほどの思いに囚われ、有子は正視できなかった男の顔をまじまじと眺めた。もしかして、この幽霊が自分を追ってきた行生の仮の姿だとしたら、あるいは行生が遣わした男だとしたら、いったいどうしたらいいのかと動揺したからだった。 行生はこの世で一番会いたくもあるが、一番忌避したい人間でもあり、何かあれば真っ先に連絡してほしい人間であるが、死ぬまで消息を知らなくてもいい人間でもあったのだ。愛しているのに憎しみでいっぱい。こんな複雑で深い感情を持った相手はこれまでいなかった。しかし、男は行生ではなかった。また行生の意志を伝えてくれるほど親切そうな様子もしていない。三十四歳の行生よりもっと若く、色黒でやや顎の張った荒々しい顔付きをしている。大きな目は空に吊られたように上がって眼差しは強く、躍る好奇心と逸る決意に満ちている。幕末の写真でよく見た顔だと有子は思った。男が、有子の顎の辺りを眺めながら早口に喋っていた。 男のやや伝法な口調が有子の恐怖を和らげた。「私が世界の果てにいるって言うの」「そう。新しい世界で、新しい生活が始まるなんて幻想だ。これまでのすべてを引きずって、あんたの世界の最果ての場所に来たんだ」有子はいきなり現れた見知らぬ男と会話している不思議さも忘れ、窓辺を振り返った。月光は変わらず降り注いでいる。外は暗闇。世界の果てにいる、と言われた寂しさが有子を襲っていた。「どうしたら戻れるのかしら」「戻りたい?どこに」男は苛立ったように舌打ちした。「だって、果てにいるよりは真ん中に戻りたいもの。果てにいるのなら、落っこちてしまうかもしれない」男は笑った。「果てに来てしまったと思ったら、どんどん知らない場所に行けばいいんだよ。 それが最果ての最前線になるだろうさ。船乗りは皆、そう思う」「船乗りなんですか」「そうだよ」「あなたは誰ですか」この問いを発した時すでに、有子は男が幽霊であることを承知していた。ここに人間が居るのだとしたら、物の怪であることは間違いない。しかし、もう恐怖は感じない。今の有子にとって一番怖いのは、向き合わなくてはならない自分の心の虚ろの方だったからだ。「あんたの良く知っている人間だよ」男は笑いを含んだ声で答えた。それなら、松村行生しかいない。 だが、行生とは東京で別れて来たばかりだ。それに男が行生であるはずがない。顔も声も何もかもが違う。不意に、今すぐ行生に会いたいという痺れるほどの思いに囚われ、有子は正視できなかった男の顔をまじまじと眺めた。もしかして、この幽霊が自分を追ってきた行生の仮の姿だとしたら、あるいは行生が遣わした男だとしたら、いったいどうしたらいいのかと動揺したからだった。行生はこの世で一番会いたくもあるが、一番忌避したい人間でもあり、何かあれば真っ先に連絡してほしい人間であるが、死ぬまで消息を知らなくてもいい人間でもあったのだ。愛しているのに憎しみでいっぱい。こんな複雑で深い感情を持った相手はこれまでいなかった。しかし、男は行生ではなかった。また行生の意志を伝えてくれるほど親切そうな様子もしていない。三十四歳の行生よりもっと若く、色黒でやや顎の張った荒々しい顔付きをしている。大きな目は空に吊られたように上がって眼差しは強く、躍る好奇心と逸る決意に満ちている。幕末の写真でよく見た顔だと有子は思った。 |
|||