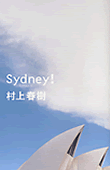 |
||||||
|
Sydney!
|
||||||
|
著者
|
村上春樹 | |||||
|
出版社
|
文藝春秋 | |||||
|
定価
|
本体価格 1619円+税 | |||||
|
|
ISBN4−16−356940−5 | |||||
|
1996年7月28日 アトランタ 有森裕子 折り返しの地点で、髪を不思議な色に染めた、すらりとしたアフリカ人のランナーとすれ違って、あいだに開いた距離を目で測ったとき、これはもう追いつけないかもしれないと思った。先頭を行くそのランナーと、自分たちの集団とのあいだには一分か、あるいは二分近くの時間差がある。彼女の走り方には追従を許さない強さがあった。脚の運びはたくましく、ストライドは滑らかで、自信に満ちていた。あのスピードは簡単には落ちないだろう。これだけの距離を詰めていくのは現実的にほとんど不可能かもしれない。こうなったらあの先頭ランナーのことは忘れるしかない。 彼女はそう思う。相手が先の方で疲れて落ちてくるのならもちろんそれでオーケー、落ちないでそのままトップを突っ走るのなら、それも仕方ない。私にできるのは、べつのところで自分のレースを組み立てていくことだけだ。でもこのアフリカ人のランナーはいったい誰なんだろう?私はこの人の名前すら知らない(彼女がファツマ・ロバという名前のエチオピアのランナーであることを知ったのは、レースが終わったあとだった)。 ファツマ・ロバが十八キロの地点で、先頭集団からするすると抜け出していったとき、集団を形成していたほかのランナーたちは、とくに気にもしなかった。あのアフリカ人ランナーはいったい誰なの?みんながそう言いたそうだった。いずれにせよ、こんな早いポイントで、あれだけの速さで飛び出したりしたら、どうせ早晩落っこちてくるはずだ。まわりのランナーたちが頭の中で何を思い、考えているか、集団の中でペースを合わせて走っていると、だいたいは伝わってくる。お馴染みの見知った顔だ。エゴロワ、シモン、マシャド。それぞれの能力も、手の内もわかっている。お互いの足音を聴き、呼吸に耳を澄ませ、心理を読みあいながら、肩を並べて走っているのだ。ロバは実績の知れない無名のランナーだ。私たちのクラブのメンバーではない。どうせあとで追いつき、吸収し、置き去りにすることになる。それがエリート・ランナーたちの共通認識だった。 彼女たちには実績と自負があった。誰もあとを追わなかった。走らせておけばいい。本当のレースは私たちが作っていくんだから。しかしオグレソープ大学わきの折り返し地点で、みんなの顔色が少し変わった。ロバはこのまま逃げ切るかもしれない。肩を並べて追走しながら、四人が四人とも本能的に同じことを感じたようだった。何かまったく新しいものごとが進行しつつあるのだ。でもその時点で(あるいはどの時点でも)彼女たちにできることはほとんどなかった。 もし誰かがあの十八キロ地点でロバについて前に出ていったら、そのランナーはたぶんつぶれてしまっただろう。そういうレースの組立ては、エリート・ランナーたちの中にはプログラムされていなかったのだ。マラソン・ランナーたちは精密に調整されたマシーンなのだ。設定が少しずれただけで、すべてのメカニズムが狂ってしまう可能性がある。 ロバの存在は忘れよう、と彼女は思った。そして忘れた。次に気になったのは、ほかの二人の日本人選手のことだった。折り返しのすれ違いでは二人の顔は見えなかった。ある程度の距離が開いているということだ。つまり、優勝圏内にいる日本人選手は私だけということになる。それでいい、と彼女は思った。二人に対して個人的な敵愾心があるというのではない。がんばってほしいとは思う。しかしそれは、私が相手として闘っているものごとのひとつのしるしなのだ。 私は勝たなくてはならない。ほかの日本人ランナーの後塵を拝するわけにはいかない。アトランタの競技場のスタートラインについたとき自分には何かができるという確かな気持ちがあった。スタートラインについたときには、もう勝負はほとんど決まっている。それがマラソンというスポーツなのだ。どのように自分をスタートラインまで運んでくるか、それがすべてなのだ。あとは四十ニキロのコースの中で、実際に確認するだけのことだ。やるだけのことはやった、彼女はそう思う。脚や筋肉や血の中に、彼女は静かな手応えのようなものを感じとることができた。 涼しい、曇った朝だった。気温は二十度、湿度は八○。パーセント。早朝に激しい雨が降り、そして上がった。路面にはまだ水たまりが残っている。ときどき思い出したようにぱらぱらと細かい雨が降った。夏のマラソン・レースとしては理想的な気候だ。もっともっと暑くてもよかったんだけれど、と彼女はひそかに思う。暑い中で我慢をする展開になれば、勝機は出てくる。そういう厳しいレースが得意なのだ。条件がきつくなればなるほど、生来の粘り強さが発揮される。それとは逆に、涼しい好条件の中でみんなが調子よく飛ばしはじめると、そのぺ−スについていくのはいささかきつくなるかもしれない。しかし予想外の涼しさの中でも、レースは落ち着いた。ペースで進んだ。ランナーたちはお互いを牽制しあっていた。なにしろビッグ・ゲームなのだ。 無謀な冒険はできない。コースの激しい高低差も不安要因だ。エリート・ランナーたちはまわりをちらちらと眺め、お互いのペースを用心深くチェックしながら、だいたい予想されたとおりのスピードで走っている。大丈夫、これならじゅうぶんについていける。仕掛けることもできる。悪くない展開だ。このまま三十キロまで行ってくれたらな、と彼女は思う。まず飛び出したのはドイツのエース、ピッピヒだった。暑くなる前に独走してできるだけ差をつけてしまおうという作戦なのだろうが、走り方にはいつもの鋼のような切ればなかった。十七キロの地点で彼女は後続集団の中に吸収され、後方に消えていった。 ドーレも耐えかねたように後ろにさがった。残っているのはシモン、マシャド、エゴロワ、名前を知らないすらりとしたアフリカ人のランナー、そして彼女の五人。十八キロの地点でアフリカ人のランナーがするりと前に出た。こんなのんびりした。ぺ−スにつきあっていくのは、もう我慢できないとでもいうように、ごく自然に。当たり前のことのように。ストライドが大きくなり、あっという間に距離が開いた。彼女のことは忘れよう。そして忘れた。そう、良いことがひとつあった。この四十ニキロのコースの中で、ひとつだけ苦手なポイントがあった。何度か試走して、そのたびに嫌な思いをした地点だった。 何故かうまく上ることのできない上り坂。その場所のことを思うと、いつも気持ちがひるんだ。でもレースの当日は、その地点を通り過ぎたことにすら気がつかなかった。ひまわりが見えたからだ。ひまわりの大きな看板が見えた。鮮やかな黄色の看板。大きいからずっと遠くからでも見える。ひまわりは彼女の大好きな花だった。オリンピック出場を決めた北海道のマラソンでも、ひまわりは彼女を勇気づけてくれた。みんなもそれを知っていて、よくひまわりを贈ってくれる。 たぶん誰かが自分を応援するために沿道にひまわりの看板を作ってくれたのだろう。しかしそれにしても、この大きさときたら!でも近づいてみると、マーガリンの広告看板だった。自分の勘違いに気がついて、彼女は思わず笑ってしまった。そうだよね、いくらなんでも私一人のためにあんなに巨大なものを作るわけはないもの。びっくりしているうちに、もう坂は終わっていた。うん、これで大丈夫だ、やれる、と彼女はあらためてうなずいた。ここは自分のためのコースなんだ。何も恐れることはない。折り返して少し進んだところで、疲れ始めていることに気がついた。脚がいくらか重くなっている。 まだたいした疲れじゃない。まわりの選手たちだってこれくらいの疲れは感じ始めているはずだ。彼女はもう一度深く耳を澄ませる。ライバルたちの呼吸の乱れを聞き取ろうとする。離れたりくっついたりするときの速度の切り替えのスムーズさに注意を払う。誰に余裕があり、誰に余裕がないか、それを探る。こうもりが闇の中で音波を送ってはねかえりを計算するように、相手の反応を感じとろうとつとめる。 そのようにじっと観察していると、これから誰が落ちていくことになるか、だいたい識別できる。あとは彼女たちをどこでどのようにふるい落とすかだ。ふるい落として、あきらめさせる。結論。注意しなくてはならないのはエゴロワ、あとはなんとかなる。少し後ろにさがったドーレのことも気になった。ドーレはしぶといランナーとして定評がある。最後まで気をゆるせない。でもなんといってもエゴロワだ。彼女に尽きる。体力もあり、頭もいい。「ああ、またエゴロワと一緒なんだ」と彼女は走りながら思う。でも宿敵だという気持ちはほとんど湧いてこない。不思議な連帯感さえ抱いてしまう。そして誇りのようなもの。 ここで再び一緒に走っているんだという喜び。ある種のおかしみ。それが実現できたんだという達成感。エゴロワの走りは相変わらず安定して確かだった。きっちりとした力強いフォームだ。しかし横になり後ろになりじっと観察していると、エゴロワの走り方には、何か一枚薄い膜がかぶっているような違和感があった。かすかな疲れのようなものが感じとれた。いつもとは何かが違う。 バルセロナのときの、あの理不尽なほどの強さは感じられない。ぐんぐん前に出て行く迫力がない。バルセロナのときのこの人はほんとにすごかったものな、と彼女は思う。しかし調子が多少良くても良くなくても、エゴロワがもっともタフな相手であるという事実に変わりはない。勝負は三十キロの地点だ。最初から気持ちは決まっていた。そこから始まる長い下り坂で勝負を仕掛ける。それが唯一の作戦らしい作戦だった。話は単純なのだ。彼女は下り坂を得意としている。、どちらかといえば上りは不得手だ。もし四十キロ手前の上り坂での勝負になったら、エゴロワには勝てないかもしれない。 だからこの下り坂が見えたら思いきって飛ばす。ほかのランナーたちを振りきる。できる、だけ差を大きく開く。おおよそニキロで下り坂は終わり、終わったところがらすぐに上りが始まる.急激にギアをチェンジしなくてはならない。下りで思いきり飛ばしたあとの上り坂は、ものすごくこたえる。これくらいきついものはない。でも耐えるしかない。耐えて耐えて坂を登り切る。うまくいけばそのままゴールまで持ち込める。うまくいけば。うまくいかない場合のことは考えないようにしよう。うまくいくときのことだけを考える。なんといっても私には耐える能力があるのだ、と彼女は思う。身体的に見れば、私より才能のあるランナーはいっぱいいるだろう。でも私くらい苦しみに耐えられるランナーはそんなにはいない。 三十キロから始まる下り坂、それが彼女にとってのレースの肝だった。何があっても、たとえどんな状況にいても、この下り坂は全力で飛ばす。彼女は心を決めていた。誰よりも速く走り、少しでも前に出ていく。三十キロは仕掛けるにはポイントとして早すぎると人は言うかもしれない。しかしそんなことは問題ではない。三十五キロで仕掛けようが、三十八キロで仕掛けようが、勝つときは勝てるし、勝てないときには勝てない。そういう問題ではないのだ。予定通り三十キロで前に出た。三十キロのスプリット・タイムを腕時計で確かめてから、ギアを素早くトップに入れる。しばらくは誰もついてこられないはずだ。 後ろはほとんど振り返らなかった。振り返っているような余裕はない。ここしかない、とめいっぱい走った。このスピードについてこられる選手がいるとしても、たぶん一人くらいだろうと思った。その一人はたぶんあの人だろう。不安がないといえば嘘になる。坂を下り終えて、上りにかかるときに一瞬、ひやりとした不安に襲われた。ひょっとしたら自分にはやりとげられないかもしれないという、ぞっとするような疑念だった。でもあくまで一瞬のことだ。それはやってきて、そして去っていった。上り坂は予想を超えて過酷だった。走っている途中で自分が少しずつ死んでいくのがわかった。脚が上がらなくなってくる。 ストライドが前に伸びない。脚のエネルギーが刻一刻涸渇していくのがわかる。体感としてわかるのだ。三十三キロ過ぎのスポンジ・テーブルのあたりで誰かが追いついてくる気配があった。足音がひたひたと聴こえた。背後のランナーに対する応援の拍手と歓声が徐々に近づいてきた。反射的に後ろを振り向いた。エゴロワだ。やはりエゴロワだ。ほかには誰もいない。彼女一人だけ。思ったとおりだ。そんなに簡単に勝たせてはくれない。エゴロワは上り坂を利用して確実に距離を詰めてきた。やがて横に並び、一呼吸置いてから抜き去った。これじゃバルセロナと同じ展開じゃないか、と彼女は思った。でも同時にそのことを嬉しいとも思う。もう一度繰り返せるんだ。もう一度それがめぐってきたんだ。でもバルセロナのときと同じようにはいかなかった。 抜かれたら、そのまますっと離された。死ぬこと。エゴロワに抜かれた時点で脚が停まった。それはすっかり死んでしまった。なんとしてでもエゴロワにしがみついていこうという積極的な気持ちはもう絞り出せなかった。どこをどう探しても、そんな余裕はない。それだけめいつぱいの走り方をしてきたし、消耗は既に限界を超えていた。こうなったら作戦も何もない。あとは粘って、粘り抜くしかない。前のランナーを抜けないのなら、ついていく。ついていけないのなら、距離を開けないことを考える。フォームもどうでもいい、メダルもどうでもいい。頭の中にあるのは《とにかく粘る》ということだけだ。めったに人を褒めない監督が、ひとつだけいつも褒めてくれることがある。「お前は脚が死んでもスピードが落ちないね。駄目になっても、ど−んと駄目にはならない。それだけは誇りに思っていいよ」本文P.8〜19より |
|||