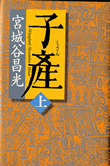 |
|
||||||||
|
子 産 (しさん)
|
|||||||||
|
著者
|
宮城谷昌光
|
||||||||
|
出版社
|
講談社
|
||||||||
|
定価
|
本体 1700円(税別)
|
上/下 | |||||||
|
|
ISBN4−06−210382−6
(上)
|
ISBN4−06−210383−4(下) | |||||||
 |
|||
|
巻一 天才の季節 十一歳の少年の目に、大人たちのうごきは、周章狼狽のようにうつった。 ─この小国は・・・・・・。 と、少年はつぶやき、すぐに語気が萎えた。自国の外交における信義のなさにあきれるし かない哀しさを感じだということである。 少年の名は、 僑 という。僑とは、神が旅行するという意味をもつ。かれは、鄭の君主であった穆公・蘭の 孫として生まれたので、ふつう公孫僑とよばれるのちのあざなをもち、 子産 と通称される。僑は自国を小国といったが、それは北の晋や南の楚のような大国にたいし てのことで、この時期、つまり春秋時代のなかばに、鄭は東隣の衛や宋とおなじ規模の国力 をもち、南隣の許、察、陳などの国よりは大きい。 脳みのない国などない。 正義をこのむこの少年にもそれはわかる。が、おなじ悩むのであれば、正義をめざして悩 みたい。 ─だが、正義とは何であるのか。 むろん、正義とは人がふみおこなうべき正道であることは理解している。しかしながらこ の戦乱の世に生まれ、しかも小国の貴族として生きてゆかねばならない自分にとって、正義 とは何であるのか、とつきつめて考えはじめると、ばくぜんとわかっていたものが、あたか も雲や霧のように実体のないもので、けっしてつかみえないものであることがわかる。 この少年は勤勉家である。 家中には史官がおり、かれに就いて学問をしている。壮年の史官で、つねに陰気さのなか で寡黙を保ってきた男である。この男が、当主である子国から、 「橋の学問をみてやってくれ」 と、いわれると、幽かにわずらわしさを目もとにあらわした。ところがである。橋を教え はじめたかれは、人が変わったのではないかとおもわれるほど、情熱家の相貌をみせはじめ た。ついにかれは熱い息で、 「主よ、僑さまは、百年にひとりの英才かもしれません」 と、いった。僑の理解力はおどろくべきもので、その強記ぶりも比類ない。 天才とはこのことか。 ものにおどろくということを忘れたようなこの史官が、腹の底から感嘆したのである。か れはすでに引退した父から学問をさずけられ、僑とおなじ年ごろの子に学問をさずけるだけ で、自家にたくわえられた知識をけっして衆前にさらすということをしない。その知識は主 家のためだけにあり、諮問に応じるべきもので、その諮問というのは、おもに、 「こういうことをしたいのだが、吉か凶か、占ってみよ」 という占辞を求めるものである。この時代、占いには二種類ある。蓍をもちいる筮占と亀 甲をもちいる卜占があり、小事を占うのは筮で大事を占うのはトといういちおうのきまりが ある。人相を観る者があらわれるのは、春秋時代の後期であるから、占いにも流行があった わけで、ちなみに獣骨を灼いてそのひびで占うやりかたは、すでに廃れていた。筮占が後世 では庶民の手のとどく占いになるというひろがりをみせたのにたいして、亀甲を灼いてひび を読みとるのは秘法といってよく、門外不出の文献によらなければできないため、伝承力が 弱く、戦国時代には消滅してしまった。 筮占の教本を易という。易には三流派があり、連山、帰蔵、周易がそれにあたるが、鄭の 公室は周王室の分家であるから、易の主流は周易であったであろう。ついでにいえば、易は のちに周易だけが残った。 |
|||
|
BOOKS ルーエ http://www.books-ruhe.co.jp/
・・・・・・HOME・・・・・・
|
|||