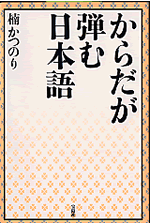|

声のパンチ、言葉のパンチ
●自己紹介
わたしはハンディーなデジタルビデオカメラを使って映像表現をする映像作家の他に、「詩のボクシング」を主催する日本朗読ボクシング協会の代表をしている。
日本朗読ボクシング協会とは、やっていることが「詩のボクシング」なので、実際のボクシングに関係させて遊び心で付けた任意の団体名。
代表とはいっても、そこでわたしは雑用係のようなものをやっている。
とにかく何でもかんでもやらなくてはならない。
時には選手としてリングで闘うこともある。
そのときは、声としての言葉を強く意識した存在として自らを「音声詩人」と呼ぶことにしている。
●「詩のボクシング」とは何か?
はじめに「詩のボクシング」について説明しよう。
「詩のボクシング」とは、ボクシングリングに見立てたリングの上で、二人の朗読者が交互に自作を朗読し、自分の“声の言葉”をどちらがより観客に伝えたかを競う『言葉のスポーツ』、『言葉の格闘技』である。
朗読の制限時間は各3分。
楽器やBGMは使えない。
肉声のみで朗読する。
わたしは、勝敗を背負ってリングに上がる朗読者を『朗読ボクサー』と呼んでいる。
勝敗の判定基準は、朗読ボクサーのくり出す声と言葉が「どれだけ観客に届いたか」にあり、判定そのものは観客の代表である複数のジャッジによって下される。
「詩のボクシング」は言葉を伝えることに真剣になれるゲームだ。
マーシャル・マクルーハンの著書『メディア論』には、ゲームは社会の縮図として機能し、その遊びを通して子どもたちは社会そのものを学ぶ、とある。
「詩のボクシング」の場もまた、社会の縮図として機能し、そのリングに上がった朗読ボクサーたちは他人を知り、社会性を身につけることになる。
面白いものは理屈ではなく、遊び心のある人たちによって広まっていくものだ。
その遊び心のある人たちによって、最初の「世界ライト級王座決定戦」と名付けたタイトルマッチが1997年10月に行なわれ、詩人で作家のねじめ正一選手が初代チャンピオンとなった。
翌98年には、現代詩最強の詩人、谷川俊太郎選手が、ねじめ選手より朗読王の座を奪取。
その闘いについては本書の最後に紹介しよう。
この世界戦の一方でわたしは、1999年の7月に一般参加によるトーナメント戦の地方大会をスタートさせた。
その流れは次第に大きくなり、2001年5月に第1回「詩のボクシング」全国大会を実現させるまでになった。
本文P.5,6から引用
|