|
|
||
|
著者
|
福井 晴敏 | |
|
出版社
|
講談社 | |
|
定価
|
本体価格 1700円+税 | |
|
第一刷発行
|
2002/12 | |
| ISBN 4-06-211528-X | ||
|
|
||
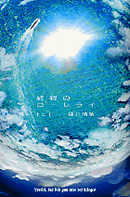 |
1945年8月。日本。 戦争。 ――その潜水艦は、あてどない航海に出た。太平洋の魔女と恐れられた兵器“ローレライ”を求めて。「彼女」の歌声がもたらすものは、破滅か、それとも―― |
|
|
絹見真一
|
|||
|
しんと凍てついた空気が、冷たさを感じさせるのか?
|
|||
|