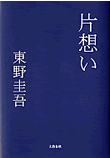|
第一章
1
四年生の時のリーグ戦に話題が移ったので嫌な予感がした。どうせまたあの話になるんだろ、と哲朗は思った。俯き、ビールを飲む。少しぬるくなっていた。
「ポイントはやっぱり第三クォーターのフィールドゴールだ。あいつを決めていれば、その後の展開もがらっと変わってた。ところがあのキックを外すんだもんなあ。がっくりきちまったよ」その試合でラインメンとして試合に出ていた安西が、笑いながらも眉間に皺を寄せていった。
現役時代と同様に分厚い身体をしている。首も太い。あの頃と違っていることは、肩も背中も丸くなってしまった点だ。おまけに腹もスイカを入れたように膨らんでいた。
「だから何度もいってるけど、あの距離を確実に決められるキッカーなんて、そうざらにはいないんだって」割り箸を片手に口を尖らせたのは須貝だ。
現在は損害保険会社に勤務している。帝都大のエース・キッカーだった男も、今は社内ではその外見からクマさんという連名をもらっているらしい。
「あの時のフィールドゴールは三十七、八、いやもしかしたら四十ヤード近くはあったんじゃないかなあ」
須貝の解説に、安西の隣ですき焼きを食べていた松崎がむせそうになった。箸を持ったまま須貝を指した。
「こいつ、あの時のキックの話をすると、そのたんびに距離が増えていくんだぜ。前にこの話をした時には、三十二、三ヤードだっていってた」
「えっ、そんなことないよ」須貝が心外そうな顔をした。
「そうだ、そうだ、たしかにそうだ」安西が太股を叩いた。「なあ、西脇」
名字を呼ばれ、哲朗も話に加わらざるをえなくなった。
「そうだったかな」浮かない気持ちが声に現れた。
「忘れたのかよ」
不満顔の安西の脇腹を松崎が肘で突いた。
「西脇があの試合のことを忘れてるわけないだろ」
この台詞に安西も笑った。「ははは。そうだったよな」
哲朗は苦笑いをするしかなかった。やはり歓迎できない方向に話が動きだした。
リーグ戦最終試合の話だ。その試合に勝てば、哲朗たちのチームの優勝が決定するはずだった。
「ラスト八秒」松崎は腕組みをし、ため息まじりにいった。
「あそこで決めてりゃ、めちゃくちゃに格好いいところだった。西脇マジックっていわれたな。きっと」
「早田に投げてりゃ、それが現実になってたんだ。なあ、早田。そう思うだろ」
安西は一番端の席で水割りを飲んでいる男にいった。
「さあ、どうだったかな」早田と呼ばれた男は気のない返事をした。この話題に付き合う気はなさそうだった。たぶん彼も飽きているのだろう。
「絶対に早田にパスしてりゃ決まってた」安西はしつこくいう。「あの時、俺は見てたんだ。早田はフリーになってた。エンドゾーンの左コーナーいっぱいのところさ。あのターゲットを見逃すクォーターバックはいないぜ。あとは西脇が投げるだけでよかった。めでたくタッチダウンだ。俺はやったと思ったね。ところてんまつがさ」後は続けなかった。
試合の顛末がどうであるかは、ここにいる全員が知っている。
「あの時、まさか俺んとこに投げてくるとは思わなかったよ」松崎が後を継ぐようにいった。「完全にマークされてたもんな。作戦が読まれてたんだ。敵のディフェンスバックは名手オガサワラだ。西脇が投げた瞬間、あっ終わったって思ったもんな」
哲朗は黙って聞いているしかない。色がすっかり濃くなったすき焼きを少し食べ、ビールを口に含んだ。最初に乾杯した時よりも、ずいぶんと苦い味がした。
ここにいる全員が帝都大アメリカンフットボール部の出身だった。
生活の殆どすべてをフットボールに捧げることを強いられた仲間だ。当時の部員は大半が卒業と共にばらばらになったが、東京都内に住んでいる者だけで年に一度集まることにしている。
それは今回で十三回目になっていた。場所は毎年同じで、新宿にある鍋料理店。日にちも十一月の第三金曜日と決まっている。
「帝都大の西脇といやあ、クォーターバックでは三本の指に入るといわれてたのになあ」安西が少し酔った口調でいった。
「あの時はどうしちまったのかなあ。俺たちだって考えられなかったもんなあ。あんなことになるなんてさあ」
「もういいじゃないか」哲朗はしかめっ面を作った。
「おまえらちょっとしつこいぞ。一体何年間、同じことばっかりいってるんだ。いい加減に忘れたらどうなんだ」
「いや、忘れんぞ」安西がグローブのような手でテーブルを叩いた。「俺は、入部してくれたら絶対に優勝できると先輩にそそのかされて、高校まで続けてた柔道を捨てたんだ。優勝させてくれなきゃ話が違う。もしアメフトなんかやらないで柔道を続けていたら、バルセロナかアトランタで」
「最低銅は取れてた、だろ」須貝がため息をついた。
「この話が出ると長いぞ」
「酒を飲ませて黙らせろ」松崎が笑いながらいった。
うんざりした思いでいる哲朗の前に、ビール瓶を持った腕が伸びてきた。早田だった。哲朗はコップを手にして酌を受けた。
「高倉は、今夜も仕事かい?」早田が低く落ち着いた声で訊いてきた。
「うん、京都に行ってる」
「京都?」
「華道の家元が、でっかいホールを作ったとかで、その落成式を兼ねたパーティが行われている。その様子をどこかの雑誌に載せるとかで、撮影しに行ってるんだ」
「なるほど」早田は頷いて水割りを飲んだ。
「よくやってるよな。カメラマンという仕事は男でも大変なのに」
「好きだから平気だとはいってる」
「だろうな」早田はもう一度頷いた。
「高倉が来ないんじゃ、色気がなくていけねえよなろれつあ」安西が呂律の怪しい口調でいった。
哲朗の妻である理沙子は、フットボールのマネージ
ャーだった。旧姓を高倉という。ここにいる仲間たちは、哲朗たちが結婚して八年以上経つというのに、いまだに彼女のことをその頃の名字で呼ぶ。
「日浦も、ずっと会ってないな」須貝が思い出したようにいった。
「日浦ねえ、懐かしいなあ」安西がまたテーブルを叩いた。「あいつ、女子マネって感じじゃなかったよな。ルールとかゲームプランのこと、俺たちよりもよく知ってた」
「そういえば安西、よく日浦にルールのことを教わってたよな」須貝が頷きながらいう。
「女だけど大したもんだったよ。作戦のことでコーチとマジで議論してたことだってある。あいつ、今は何をしてるのかな」
「結婚して、子供もできたそうだ」哲朗が報告した。
「理沙子がいってた。でもあいつにしても日浦とは三年ぐらい前に電話で話したきりじゃないかな」
「女は結婚すると、交際範囲ががらりと変わるからな」須貝がいった。
「男だって、変わるぜ」松崎が真面目な顔になった。
「中尾の奴、今日も欠席だろ。結婚してから付き合いが悪くなった。すっかりマイホームパ。ハに変身したらしい」
「かみさんが怖いんだよ」答えたのは須貝だ。意味もなく声をひそめている。「お嬢様ってのは、やっぱり扱いにくいらしい。すっかり尻に敷かれている。婿養子は辛い」
「やれやれ。うちが誇ったランニングバックも、女房の張った蜘蛛の巣からは逃げられなかったか」安西が徳利を引き寄せ、自分のコップに注ごうとした。
しかしそれはもう空っぽだった。
酒宴は十時にお開きとなった。かつてのアメフト部員たちは店の前で解散した。以前は二次会、三次会と流れこんだものだが、今ではそれをいいだす者もいない。誰もがそれぞれに家庭を持っており、時間も金も自分のためだけに使える立場ではなくなっていた。
哲朗は須貝と共に、地下鉄の駅に向かって歩きだした。
「よく飽きずに同じ話ができるよな」須貝がいった。
「いつまで経っても俺はあのフィールドゴールのことをいわれるし、西脇は最後のパスのことをいわれる。
優勝を逃したことは俺も悔しかったけど、もう十三年だぜ。ふつう、ふっきれないかな」哲朗は黙って笑った。安西や松崎が本心からこだわっているのでないことは十分にわかっている。
彼等は何かを取り戻したくて昔話を繰り返すのだ。
須貝の胸元で携帯電話が鳴りだした。彼は電話機を取り出し、歩道の脇に寄った。
「やあ、なんだ。さっきまで噂をしていたんだぞ。……うん、たった今、解散したところだ。隣に西脇もいる。これから地下鉄に乗ろうと思ってさ」須貝は送話口を手で押さえ、哲朗に向かっていった。
「中尾だよ」
哲朗は頷き、口元を綻ばせた。噂をすれば、というやつらしい。
「ああ、おまえ以外は全員揃った。高倉と日浦は来なかったよ。……ははは、そうだよ、男ばっかりだ。西脇なんか来なくていいから高倉には来てほしかったって、安西なんかはいってた。…-うん、みんな相変わらずさ」
須貝が話すのを、哲朗は横で苦笑しながら聞いた。
かつて俊足ランニングバックだった中尾とは、一昨年の集まり以来会っていない。
中尾の用は特に重要なものでもなかったようだ。
須貝は電話を切った。
「来年は出席したいといってたよ」
そうか、と哲朗は答えた。去年もあいつはそういったんじゃなかったかなと思った。
改めて歩きだそうとした時だった。
須貝が突然足を止めた。哲朗の後方に目を向けている。ひどく意外そうな表情で、口は半開きになっていた。
「どうした?」
哲朗は彼と同じ方向を見た。目の前の歩道を、まだ遊び足りなさそうな若者たちや、家路につこうとするサラリーマンたちが行き交っている。いつもの風景だ。
どうしたんだ、と哲朗はもう一度訊こうとした。
その時、人々の流れの向こうに、じっとこちらを見ている女性がいることに気づいた。車道を背にして立っている。
「あれは……」哲朗は咳いた。
「日浦じゃないか」
「そうだよな、やっぱり。何してるんだ、あいつ」須貝は手を振った。
そこに立っていたのは、間違いなく日浦美月だった。
ややつり上がった目と、細くて高い鼻に見覚えがあった。ただ、頬のあたりが削げたように細く、以前よりも顎が尖って見えた。黒いスカートを穿き、グレーのジャケットを羽織っている。手には大きなスポーツバ
ッグを提げていた。
美月は先程から哲朗たちのことを見ていたらしい。
二人が自分に気づいたことを察知して、人の流れを横切るように近づいてきた。その目は哲朗に向けられている。
「髪、伸ばしたんだな」須貝が隣でいった。
美月の髪は肩よりも下まであった。
茶色がかって見えるが、染めているのかもしれない。風を受け、少し乱れている。すぐに彼女だと気づかなかったのはそのせいだなと哲朗は納得した。彼の記憶にある日浦美月は、いつも耳が辛うじて隠れる程度のショートヘアだった。
しかしそれを差し引いても、彼女が発する雰囲気は、哲朗が覚えているものとずいぶん違っていた。それは年齢を重ねたことによるものでもなさそうだった。
美月は哲朗たちの前に来ると足を止め、二人の顔を交互に見た。その顔に浮かべられた笑みは、やけにぎごちなかった。
彼女と目を合わせた瞬間、哲朗は胸に軽い違和感を覚えた。異物が引っかかるような感覚だった。
彼女は唇を動かした。だが声は聞こえなかった。
「何やつてるんだよ、こんなところで。今日が十一月の第三金曜だってことはわかってたんだろ」須貝が、責めるというよりも、疑問を解決したいという口調で訊いた。
美月は謝るように顔の前で手刀を切った。それからバッグを下に置キき中から小さなノートとボールペンを出してきた。
「なんだ、なんだ、一体」
須貝が訊いたが、彼女は答えない。そのかわりにノートに何か書き込み、哲朗のほうに見せた。
『どこかで話を』そこにはそう書いてあった。
2
「どういうことだ?」哲朗は美月の顔を見つめて訊いた。「おまえ、しゃべれないのか。喉をどうかしたのか」
「風邪か?」と須貝も横からいった。
彼女はかぶりを振った。そしてノートに、さらに何か書いた。それを見せる。
『今はこたえられないくわしい話はあとで』
哲朗は須貝と顔を見合わせた。改めて美月に目を戻した。
「何があったんだ。声を出せなくなつちまったのか」
しかし美月は口を閉じたまま、ノートに書かれた文章を指すだけだった。
「変な奴だな。何があったんだ」須貝がいう。
「とにかくここでは答えられないらしい。どこかゆっくり話せる店に行こう」
哲朗がいうと、美月は眉間に皺を寄せ、激しくかぶりを振った。
「人目につく店には入りたくないわけか」彼は訊いてみた。
彼女はこっくりと頷いた。
須貝が、ふう-つと息を吐き出した。
「何だよ。人目につかない場所っていうとカラオケボックスぐらいしかないぜ」
「それでいいか?」哲朗は美月に訊いた。
彼女は迷うように首を傾げた。軽くウェーブのかかった髪が風に揺れている。
その時哲朗は、以前の彼女と一番違っている点に気づいた。それは化粧だ。前に比べて濃くなっている。
しかも丁寧にメイクしたというより、とりあえず手元にあった化粧品を塗りたくったという雑なやり方だった。
口紅も唇から少しはみ出ている。彼女が声を出さないことより、そのことのほうが彼を不安にさせた。
「じゃあ、俺のところに来るか」哲朗は思い切っていってみた。
美月は顔を上げ、彼の目を真っ直ぐに見つめてきた。
いいの、と尋ねる目だ。
「俺はいいぜ。須貝、おまえはどうだ」
「いや、もちろん俺もいいけどさ」須貝は背広の袖を少し上げて、腕時計を見た。
「こんな時間に迷惑じゃないか。ええと、高倉は今夜はいないんだっけ」
「遅くに帰ってくる予定だけど、あいつのことは気にする必要はない」哲朗は美月を見た。「どうする?俺の家なら、ここからすぐだ」
彼女は何かいいだそうに唇を動かしかけたが、結局声は発しなかった。申し訳なさそうに小さく頷いた。
「よし決まった」哲朗は須貝の背中をぽんと叩いた。
新宿三丁目から丸ノ内線に乗ることにした。
地下にもぐる前に、須貝は携帯電話で自宅に電話した。大学時代の女子マネに会ったので、これから西脇のマンシ ヨンに行くことになった、という意味のことを話して
いる。その後彼は哲朗のほうに電話を差し出した。
「かみさんが、ちょっと代わってくれといってる」
「俺にか?」
うん、と須貝は下唇を突き出して頷いた。
哲朗は電話機を受け取って挨拶した。須貝の妻とは面識がある。
披露宴にも出席した。面長の、日本的な顔立ちをした女性だった。
須貝の妻は、こんな時間にお邪魔して迷惑じゃないかという意味のことを尋ねてきた。
いや、うちならいいんですよ、気にしないでくださいと哲朗は答えた。
「きっちりした奥さんだな。それとも亭主の浮気を心配してるのかな」
「浮気なんか論外だよ。俺がどこかで飲んで帰るんじゃないかと心配してるんだ」
「飲んで帰るぐらいかまわないだろ。銀座に立ち寄るわけじゃないんだし」
「ところがそうでもないんだ。下の子が今度、小学校に上がるから{きいろいろと締め付けが厳しくなってる。おまけにローンもあるし」
去年の暮れ、須貝は荻窪のマンションを購入していた。
「おまえのところはいいな。高倉も働いてるし」
「そうでもないぜ」
三人で地下鉄の階段を下りた。その途中で美月はサングラスをかけた。どうしてこんな夜にかけるのかと思ったが、哲朗は訊かないでおいた。
丸ノ内線は混んでいた。車内で人にもまれ、須貝だけが離れた場所へ行った。哲朗は美月と共に反対側のドアまで押された。美月をドアの横に立たせ、彼女と向き合うように立った。周りからの圧力が彼女に及ばぬよう電車の壁に手をついた。電車が揺れるたびに身体の向きを調節する必要があった。まるでラインメンだと思った。
美月は彼と顔を合わせるのを避けるように、ずっと下を向いていた。サングラスの隙間から長い睡が見えた。マスカラはつけていないようだ。
車内の明かりの下で見ると、彼女の化粧のひどさがよくわかった。ファンデーションにしても塗り方にムラがある。
ずいぶんと肌が荒れているようだが、それを少しもカムフラージュしていなかった。
さらに途中で気づいたことがあった。それほど濃い化粧をしていながら、少しもいい香りが漂ってこないのだ。それどころか哲朗の鼻腔が捉えたのは、饐えたような汗の臭いだった。
汗の臭いから連想するものがあった。薄暗い廊下。
半分壊れたような開けっ放しのドア。その上に色のはげ落ちた札が掲げられていた。アメリカンフットボール部、と書かれた文字も消えかかっている。
ドアの向こうは、挨や汗、徽の臭いの混じった空気が充満した部屋だ。
プロテクターやヘルメットが乱雑に置かれた部屋の中央に一人の女が立っていた。何年も拭いていない窓ガラスから入る日差しを受けて、彼女の右半身は光っていた。
「QBの気持ちはわかってるよ」
彼女日浦美月はいった。あの最終戦の翌日のことだ。部室には哲朗と彼女以外、誰もいなかった。
それでも室内には、選手たちの熱気がこもっていた。
「あれは、あれでいいんだ。QBは悪くない」美月はさらに続け、ゆっくり頷いた。その頃彼女は哲朗のことをQBと呼んでいた。もちろんクォーターバックのことだ。
「俺のミスだよ」哲朗は答えた。「俺のせいで優勝できなかった」そして芝居がかったため息をついた。
五点差だった。十九対十四。タッチダウンを決めれば逆転という場面だった。
もともと劣勢だといわれていた。そのことは哲朗たちも覚悟していた。相手チームはランディフェンスが強い。対して哲朗たちのチームは、ランニングバック中尾のスピードが最大の武器だ。それを封じられれば勝つ見込みは薄くなる。
哲朗たちはパス攻撃に賭けた。中尾に的を絞ってくるディフェンス陣の裏をかくことにしたのだ。
哲朗たちはフェイクを増やした。つまり中尾にボールを渡す「ふり」だけをしたのだ。中尾はボールを受け取った「ふり」をし、いつものように走る。相手ディフェンスが彼の動きに幻惑されている間に、哲朗はワイドレシーバーの松崎やタイトエンドの早田にパスを繰り出した。
そのシーズンの帝都大はパスプレーが少ないと踏んでいた相手チームは完全に裏をかかれた。彼等は西脇哲朗が前のシーズンまではリーグで一、二を争う強肩クォーターバックだったということを、すっかり忘れていた。
|